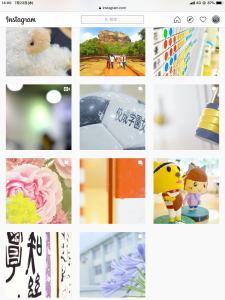皆さんこんにちは。学校長の宍戸崇哲(ししどたかのり)です。毎月1回、校長としての私の感じたことや考えを「宍戸校長の【Back to Basics】」と題して、本校HPで発信していきます。学校や生徒のことを中心に社会の出来事なども交えて、皆さんと何かを共有できればと思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。今回は「今の時代を生きる子供たちへの言葉〜終業式」と題してお届けいたします。
本日、2020年度1学期終業式を迎えることができました。私たちが今までに経験したことのない厳しく不安な社会状況が今もなお続いています。そのような中、生徒の皆さんや教職員は4月始めから心配や不安、活動が中止になり、思い通りに行かない悔しさや悲しみ、多くの不便さや不自由さを感じる困難の中で、「オンライン学校」、6月からの「段階的な学校再開」、そして「現在の平常授業」へと、それぞれの努力や創意工夫によって、「学びの場」を継続することができています。皆さん一人ひとりの努力や協力のおかげだと思い、深い感謝の念でいっぱいです。ここには明らかに今までとは違う「新しい学校の日常」があります。感染予防の観点から始まった多くの取り組み、例えば、時差登校、オンライン環境での授業、HR、会議、面談、研修、部活動、などが、今後はこれまでとは全く異なるポジティブな意味を持って、様々な学校の教育活動の中に、自然に溶け込んでくると思います。
私がメディア取材を受ける中で、「現在のコロナ禍を生きる子供たちに、どんなことを伝えたいですか」と問われることがあります。今日はその時に話したこと、新たに考えたことを伝えたいと思います。
私は「現在2020年の世界情勢は、間違いなく、人類の歴史の中で大きな転換期であり、その時に若者としての自分が存在して、自分がその変化の一部となっていることに気づく、さらにできれば、皆さんがこの大変化に自らが影響を与える勇気を持ってほしい」ということを伝えたいと思います。苦労や困難に対応していくことに心がとらわれてしまうのは当然のことですが、一方で、新しく社会的な進歩発展が同時に進んでいるという意識を持つことができたらと思います。正解も不正解も分からない中で、自分の小さな気づきや思いつきを他者に表現して形にすることに、果敢に取り組んでいくことはとても大切なことだと思うのです。日本の長い歴史の中で現状を捉えると、幕末から明治への歴史の激動期、あるいは第2次世界大戦前後の時期にあたるか、それ以上の、世界の社会変化の最中に、皆さんは若者として存在するという感じでしょうか。コロナ禍を受動的に生きていくのではなく、この時代に中・高生である運命の巡り合わせを感じて、自らが前向きにこの苦難に関わる気持ちを持ってくれると良いと考えます。
過去においてもそうであったように、今年の皆さんの毎日の小さな体験や感情などを、未来の子供達に伝える時がきっとくるでしょう。それだけ人類にとって大きな意味を持った瞬間を過ごしていることに私たちは意識を向けていかなければなりません。
そして、このような時だからこそ、これまでの常識にとらわれない、考えやモノを生み出すこともできると考えてほしいのです。私たちの現在の日常には多くの心配や不安、苦労や困難があります。さらに生活の中で不便さや不自由さが溢れています。しかし一方で、その不便さ・不自由さを乗り越えるために、新しいアイディアや小さな試みがたくさん存在していると思います。皆さんの方がもっと多くのことを知っていると思いますが、例えば、外出できないことが多い現在、オンラインで遠くにいる祖父母と話す。VRでロンドンナショナルギャラリー館内を廻り、名画を鑑賞する。Google Earthで世界遺産をめぐる。食事の宅配サービスを使って、都心のお店からスイーツを取り寄せる。ゲームソフト内で自分のキャラクターに実在のファッションブランドの服を着せ、友達と楽しむなど。つい最近までは存在しなかったような仕組みが現実に存在します。このように、大変化の困難を極める時代にはその苦労を乗り切ろうとする思いから、多くの新しい取り組みや仕組みが生み出されます。社会では、creativity(創造性)を持った人や企業が注目され、加速度的に日常生活の中身が変わっていきます。教育の中でも、これからこの力を育てる教育活動がさらに重視されていくと思います。実は皆さんはすでにその基礎を学び始めていますが、人間力養成、国際理解や異文化理解、探究学習、ICTの学びなどの土壌に、他者のため、社会のために役立つものや仕組みを生み出すクリエィティブな力を開花させてほしいと思います。
本校は今まで同様、生きる力、考える力、何かを生み出す力を身につけていく皆さんを支えていきたいと思います。
最後になりますが、生徒の皆さんと教職員のこれまでの大変な努力のおかげで、本校は明日から8月31日まで夏休みをとることができます。この貴重な時間を、健康に十分留意しながら、受験準備、学校の各活動、講習や研修、個人的に休校期間にできなかったことに取り組むようにしてください。
まだ苦しく厳しい時は続きますが、ここまで苦難を乗り越えてきた互いの力を信じて、これからも力を合わせて努力を続けていきましょう。