 9月13日(火)に、中学1年生が「サイエンスプロジェクト」・「北海道プロジェクト」の一環として三笠市立博物館を訪問しました。三笠市立博物館・野外博物館の見学、アンモナイトのレプリカづくりを体験しました。
9月13日(火)に、中学1年生が「サイエンスプロジェクト」・「北海道プロジェクト」の一環として三笠市立博物館を訪問しました。三笠市立博物館・野外博物館の見学、アンモナイトのレプリカづくりを体験しました。
三笠市立博物館では、約600点以上もの北海道産の「アンモナイト」の化石や、国の天然記念物に指定された「エゾミカサリュウ」の化石、等身大の恐竜の模型等が展示されており、アンモナイトや恐竜のわかりやすい解説が見られる大型モニターを活用しながら1億年前の世界を体験することができました。
野外博物館では、ガイドさんの懇切丁寧な解説を聞き、1時間以上かけて全長1.2 kmのサイクリングロードを散策しながら、動植物や地層の観察をすることができました。そこでは、垂直に隆起した泥岩、砂岩、礫岩(れきがん)からなる約1億年前の白亜紀層と、石炭層を含む約5000万年前の古第三紀層を観察できるだけではなく、明治時代以降に三笠市でさかんであった石炭産業にたずさわる人々のくらしや三笠での炭鉱の歴史も知ることができました。
アンモナイトのレプリカづくりでは、5種類のアンモナイトの化石から取った型枠の中から自分の好きな型枠を選び、その中に石膏を流し込んで制作しました。生徒たちは自分だけのレプリカを制作しようと、集中した表情で作業に取り組んでいました。完成したレプリカは記念として持ち帰ることができました。
今回の三笠ジオパーク研修で、実際に見るという直接的な体験ができたことにより、中学1年生で学習する地学の地層分野を深く理解することにつながりました。三笠市立博物館の学芸員さん・ガイドさんには大変お世話になり、ありがとうございました。





 月23日(土)と24日(日)の2日間、第37回北嶺祭が行われました。コロナ禍ということで、残念ながらすべてが例年通りということにはなりませんでしたが、換気・感染症対策を徹底した体育館での企画のほか、多くの校舎内企画を実施することができました。 中学生は「国」をテーマにクラスごとの展示を行いました。教室内の装飾のほか壁新聞やステンドグラス、アトラクションなど工夫を凝らしての発表でした。1年生ははじめての北嶺祭ということで、準備期間から一生懸命協力し、レベルの高い展示内容となりました。
月23日(土)と24日(日)の2日間、第37回北嶺祭が行われました。コロナ禍ということで、残念ながらすべてが例年通りということにはなりませんでしたが、換気・感染症対策を徹底した体育館での企画のほか、多くの校舎内企画を実施することができました。 中学生は「国」をテーマにクラスごとの展示を行いました。教室内の装飾のほか壁新聞やステンドグラス、アトラクションなど工夫を凝らしての発表でした。1年生ははじめての北嶺祭ということで、準備期間から一生懸命協力し、レベルの高い展示内容となりました。 7月16日(土)、高校2年生バギー乗車練習会を行いました。教育施設として登録されている北嶺裏の私有林の林道を整備し、北嶺周辺の豊かな自然環境を有効活用するための取り組みとして、北嶺にはバギー車が5台用意されています。校舎裏庭の駐車場で練習会を行い、十分な技術を身につけた生徒には免許が交付され、その後晴れて林道での乗車が許可されます。今回は初回の練習会で、参加した生徒たちは初めは恐る恐るハンドルを握っていましたが、すぐに慣れとても楽しそうにバギー運転をしていました。2学期には2回目、3回目と練習会を行い、林道での乗車へとつなげていく予定です。
7月16日(土)、高校2年生バギー乗車練習会を行いました。教育施設として登録されている北嶺裏の私有林の林道を整備し、北嶺周辺の豊かな自然環境を有効活用するための取り組みとして、北嶺にはバギー車が5台用意されています。校舎裏庭の駐車場で練習会を行い、十分な技術を身につけた生徒には免許が交付され、その後晴れて林道での乗車が許可されます。今回は初回の練習会で、参加した生徒たちは初めは恐る恐るハンドルを握っていましたが、すぐに慣れとても楽しそうにバギー運転をしていました。2学期には2回目、3回目と練習会を行い、林道での乗車へとつなげていく予定です。 本校伝統の校技大会である第37回高校3年生柔道大会が7月15日(金)に本校柔道場で開催されました。柔道部主将、榊原誠君の選手宣誓の後、試合前後の手指消毒や畳の消毒などの感染症対策をした上で、個人戦4階級(軽量級、軽中量級、中量級、重量級)の試合が行われました。今年度もコロナ禍での大会であることを考慮し、トーナメント方式による勝ち上がりではなく、1人1試合という形で6年間を締めくくる大会として行われました。各生徒が6年間の柔道への取り組みの成果を出し切ろうと必死に戦い、手に汗握る試合の連続でした。全ての生徒が自分の力を出しきり、北嶺での柔道を終えることができました。
本校伝統の校技大会である第37回高校3年生柔道大会が7月15日(金)に本校柔道場で開催されました。柔道部主将、榊原誠君の選手宣誓の後、試合前後の手指消毒や畳の消毒などの感染症対策をした上で、個人戦4階級(軽量級、軽中量級、中量級、重量級)の試合が行われました。今年度もコロナ禍での大会であることを考慮し、トーナメント方式による勝ち上がりではなく、1人1試合という形で6年間を締めくくる大会として行われました。各生徒が6年間の柔道への取り組みの成果を出し切ろうと必死に戦い、手に汗握る試合の連続でした。全ての生徒が自分の力を出しきり、北嶺での柔道を終えることができました。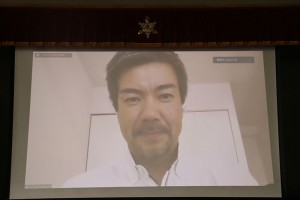 7月11日(月)、北嶺8期の卒業生で、現在日本政府国連代表部一等書記官としてご活躍の山口知也さんの講演会を全校生徒が参加して実施しました。「ウクライナ情勢:国連の役割と限界」と題し、国際秩序の根幹を揺るがすロシアによるウクライナ侵攻を前に、「国連は役に立っていない」という批判があるがそれは正しいのか、そもそも国連の役割とは何か、国連ができることは何なのか、日本には何ができるのか、などについて、ニューヨークの山口さんからオンラインでご講演いただきました。山口さんからは、国際社会への理解について、「国際社会には驚くほど多様な立場・考え方がある。異なる国・人々の多様な考え・背景事情に関心を持ち、想いを馳せる気持ちを持ってほしい」というメッセージをいただきました。
7月11日(月)、北嶺8期の卒業生で、現在日本政府国連代表部一等書記官としてご活躍の山口知也さんの講演会を全校生徒が参加して実施しました。「ウクライナ情勢:国連の役割と限界」と題し、国際秩序の根幹を揺るがすロシアによるウクライナ侵攻を前に、「国連は役に立っていない」という批判があるがそれは正しいのか、そもそも国連の役割とは何か、国連ができることは何なのか、日本には何ができるのか、などについて、ニューヨークの山口さんからオンラインでご講演いただきました。山口さんからは、国際社会への理解について、「国際社会には驚くほど多様な立場・考え方がある。異なる国・人々の多様な考え・背景事情に関心を持ち、想いを馳せる気持ちを持ってほしい」というメッセージをいただきました。
