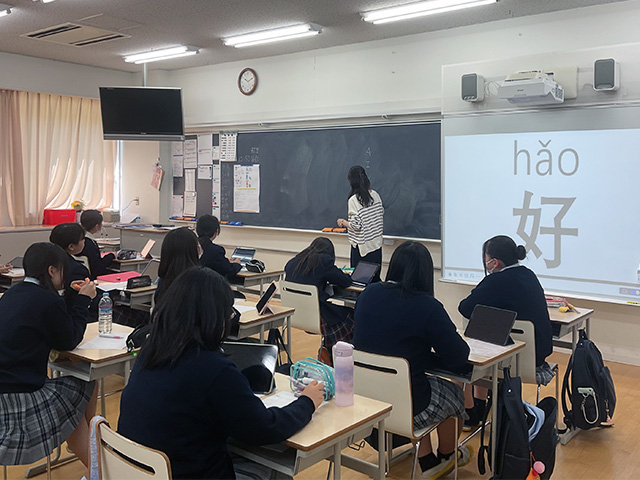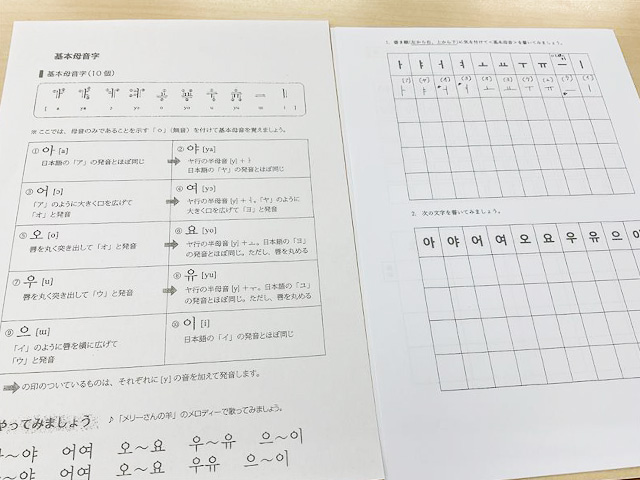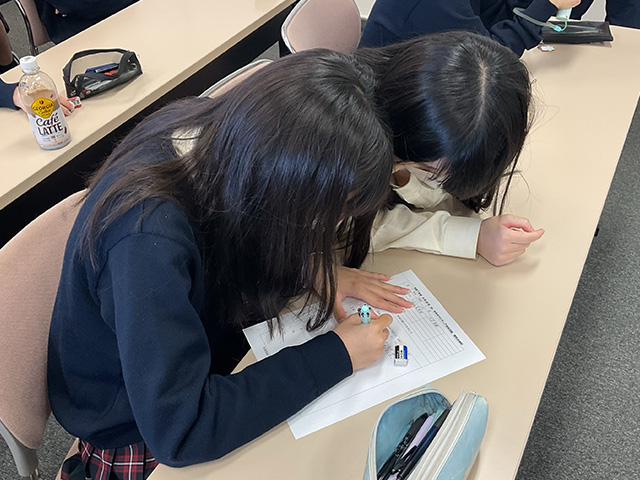顧問より 「今回の合宿は、駒女野球部としては初めての試みでした。 夏の大会を2か月後に控えるところにあって、練習をやりこむ必要性があり朝から寝る直前まで野球漬けになりました。 3泊4日(実質練習日程は3日間)という期間は、短いようで長く感じた選手も多いかと思いますが、終わってみればあっという間に終了したのではないかと思います。」

キャプテンより 「今回の合宿では、さまざまな活動に取り組みました。3日間の練習を通じて得られた学びや気づきを振り返ります。合宿での練習はいつもとは違う土のグラウンドで実践形式を中心に行いました。その中で、中継プレーに関して気づきがありました。普段とは広さが違うグラウンドで内野手のカットの距離が人によって大きく差があったことに初めて気づきました。それと、外野手が芝のイレギュラーを恐れあまりチャージできていなかったことで、普段あまりない中継プレーでのミスが目立ちました。しかし、最終日には同じようなミスはほぼなくなっていたのでしっかり修正できていたことはよかった点だと思います。どんなグラウンドでも、1日のその試合の中で同じミスが起きないようにすぐに修正することが大切だと学びました。 それから、就寝前には全員で素振り、メンタルトレーニング、朝も早くから体操などを行いました。そのため、日に日に疲れが溜まっているのを感じました。慣れない環境に練習、疲れが溜まってしまうのは仕方ないですが、夏の大会も同じように慣れてない環境での連戦になり、より疲れが溜まることが予想できます。その中でも、いい状態でプレーすることが大切です。今回の合宿は、それに向けてよい練習になりました。他にも、合宿で学んだたくさんのことをチームとしてもそれぞれ個人としても無駄にすることなく、夏の大会まで練習に励んでいきたいです。」

副キャプテンより 「今回の合宿では、日常の練習では得られない多くの学びと気づきを得ることができました。朝から晩まで野球漬けの生活の中で、基本の反復練習や実戦形式のメニューを通して、各々の技術の課題を明確にすることができました。また、仲間との共同生活を通して、チームとしての団結力や、周囲への気配り・協力の大切さを実感しました。体力的にも精神的にも厳しい場面はありましたが、その分一つひとつの練習の意味や、監督やコーチの意図を深く考える機会にもなり、とても充実した3日間を過ごすことができました。 これからの自分の目標は、技術面だけでなく精神面でも成長し、チームにとって必要とされる存在になることです。普段の練習から全力で取り組み、プレーでも声でもチームを引っ張っていけるように努力していきます。また、仲間とのコミュニケーションを大切にし、周りの選手の良いところを引き出せるような行動を意識していきたいです。チームが一つになって戦うためには、全員がお互いを信頼し合うことが大切だと思っています。 目指すのは、「このチームで本当に良かった」と心から思えるようにすること。そのために、自分にできることを一つひとつ丁寧に積み重ね、日々前進していきたいです。」