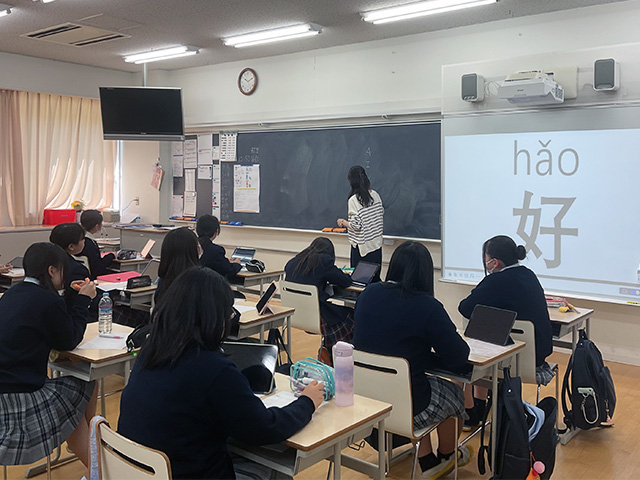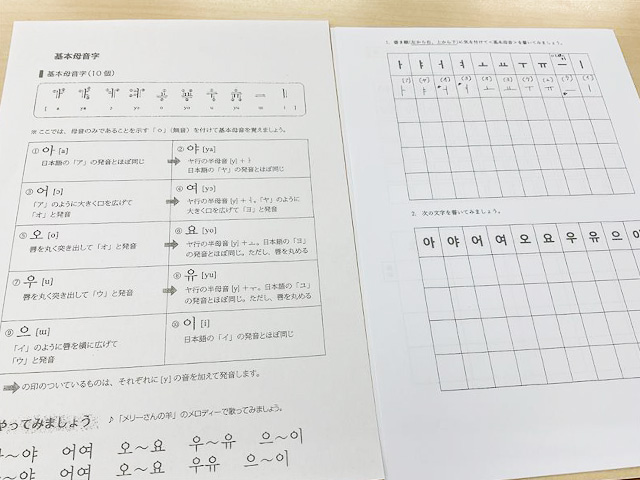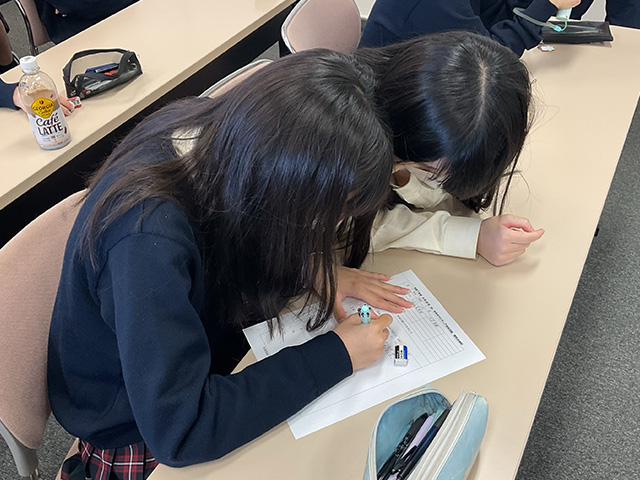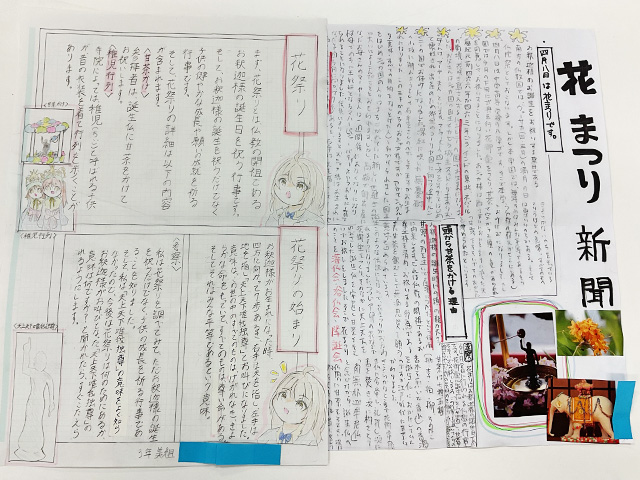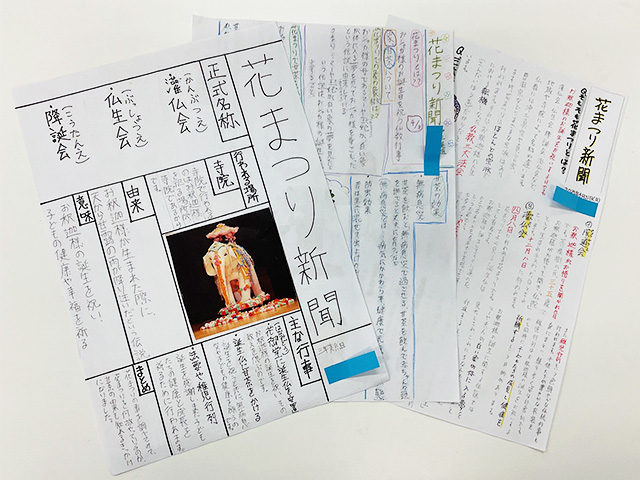5月31日(土)中学授業体験会(説明会) を実施いたします。
◎13:30~14:40 授業体験会
①英語(13:35~14:05)
「Ordering Food ~英語で注文してみよう!ファストフード編~」
②算数(14:10~14:40)
以上の授業を体験していただきます。
◎14:45~ 説明会など
その後、ご希望の方に、本校が大切にしている仏教を基盤とした人間教育の実践、
定着させ、高めるための教育内容、6年間の進路学習や進路状況などを、
生徒たちの様子などと一緒にご説明いたします。
また、校内見学・個別の相談もできます。
校舎内には、受験生お一人につき、付き添いは原則お2人までとさせていただきます。
ご兄弟がいらっしゃる場合にはこの限りではありませんので、ご一緒にご来校できます。
上履をご持参いただく必要はありません。
※ 自家用車で来校の方は正門手前左側の駐車スペースをご利用ください。
あざみ野からのスクールバスは
在校生のみとさせていただいております。
稲城長沼駅からのスクールバスはご利用できますので、ホームページにて
バスのダイヤをご確認ください。
駒沢学園女子中学高等学校 入試広報部
TEL 042-350-7123 E-mail:nyushikoho@komajo.ac.jp
受付時間/9:00~16:00
ぜひ、ご参加をお待ちしております。
詳細・お申し込みはこちらから