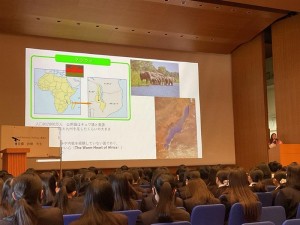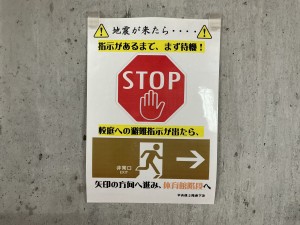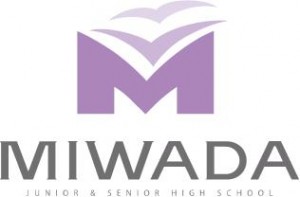12月のグループ発表を経て、先週、学年発表会を行いました。
・生成AIと人、どちらに相談した方が悩みが解決しやすいのか
・修学旅行はいつ行くべきか
・人々はなぜグループになって行動することが多いのか
・「好き」と「推し」の違いとは
・なぜ校庭の奥にだけダニが大量にいるのか
・なぜ人は他人と比べてしまうのか
・家族喧嘩は無くすべきか
・なぜ人間に、食べ物の好き嫌いが生まれるのか
・男性より女性の方が立場が低い社会構造ができてしまったのはなぜか
探究の授業では、答えを持たない問いを持ちより、どうしたらよいかわからなくても、仲間と一緒に、それぞれのテーマを研究することで、人間同士の繋がりも生まれます。
情熱の対象を探し続けること。
それを追求すること自体が生きることに意味を持たせます。
そして導き出した探究の答えにはまた多様性があります。
生徒の探究は続きます…