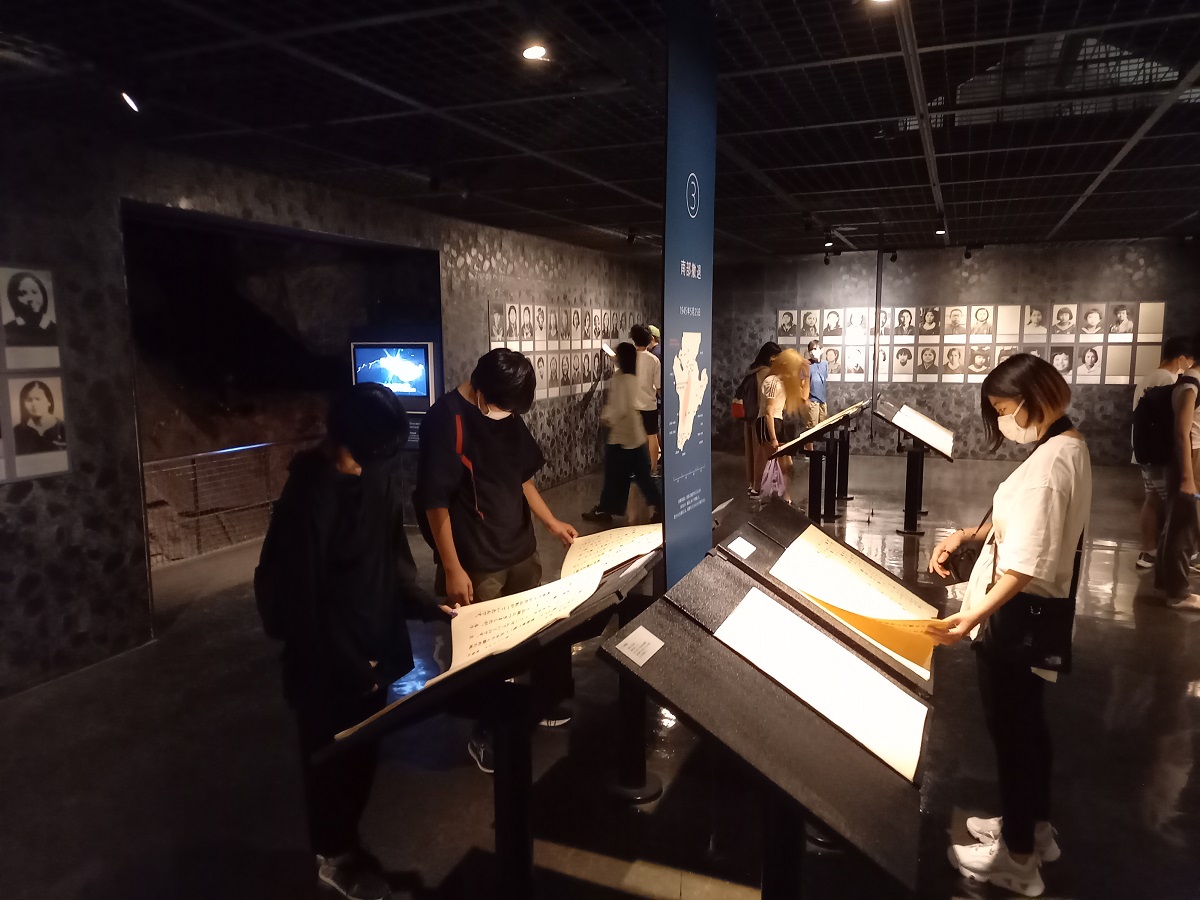7月2日・・・今日は午前中に自然・文化体験を行い、15時発のフェリーで伊平屋島に向かう予定でした。「カヌーとマングローブ」「漆喰シーサー&島草履づくり」「サンゴ再生」「琉球グラス絵付け」楽しみにしていた体験プログラムでしたが、あいにく台風4号が発生し、今夜から明日にかけ沖縄本島に最接近の模様。15時発のフェリーの欠航が予想されたため、急遽体験をキャンセル、11時発の午前便で運天港から出発しました。お昼ご飯は伊平屋島の民家の皆さんが用意してくれることになりました。感謝です。


到着した前泊港のポートターミナルには、「明星学園中学校めんそーれ~いへや島」の横断幕が。雲の切れ目から強い日差しがさしています。沖縄の海の色を見ることができました。


開村式が終わると、民家さんの車でめいめい手を振りながら出発していきます。ワクワクとドキドキの瞬間です。台風が来る前に島内観光をしてくれるようです。ここからが明星学園中学校修学旅行のハイライトです。


伊平屋島は、沖縄の島にしては珍しく水が湧き、水田が広がっています。写真をご覧いただくと分かりますが、すでに黄金色で収穫間近ということです。ここ伊平屋では米の二毛作が行われ、7月中に1回目の収穫が行われるようです。小高い山もあり、山羊が放されていました。


台風は今夜遅くに最接近しそうです。台風一過を期待したいと思います。
(中学校副校長 堀内)