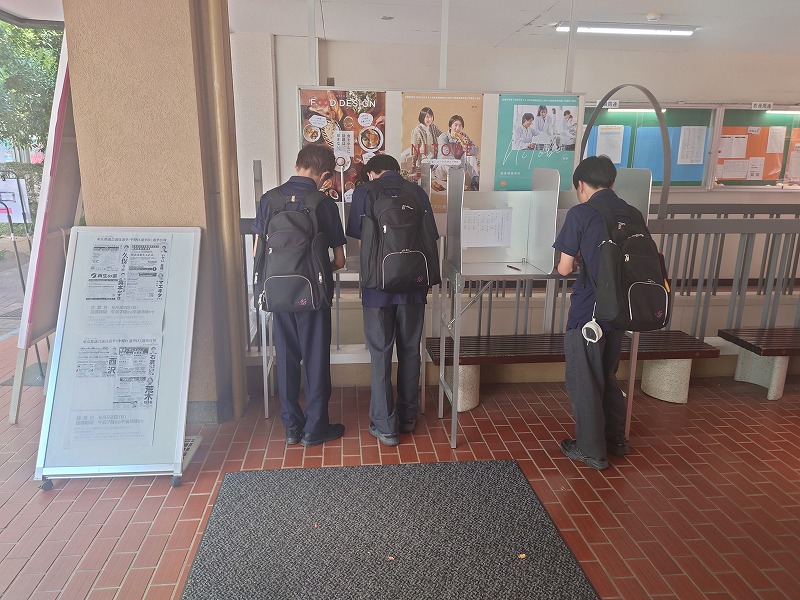皆さんは「未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS(イマジナス)」をご存知ですか?
高円寺駅から歩いて5分ほどのところにある施設で、科学を活用してわたしたちの未来を想像しながら、誰もが参画できるコミュニティを目指した場所です。
参考:イマジナスURL
6月18日(水)、中高融合ゼミ 実験教室ラボはクロスカリキュラムの時間を使ってイマジナスへ行ってきました。
イマジナスに伺う目的は「ワークショップ」の体験と「企画開発を行う手順や大切な視点」の講義を受け、実践に活かすことです。