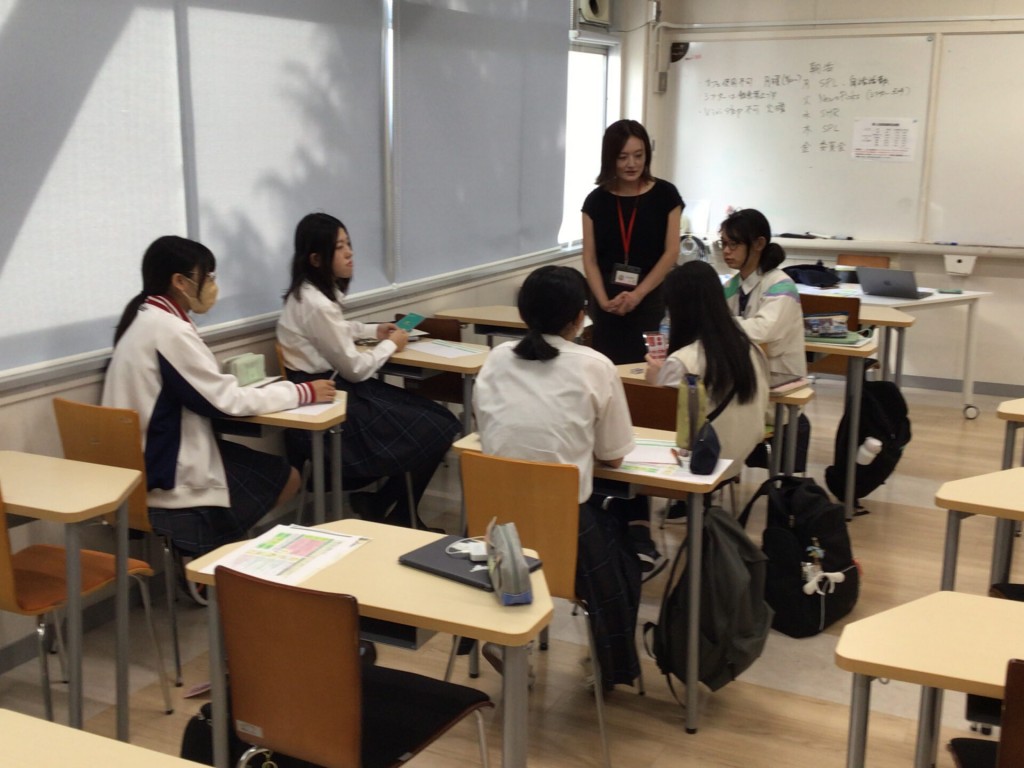今回は、先日行われた中学生の特別な学びの旅、「滋賀県琵琶湖スタディツアー」の様子をお伝えします。このスタディツアーは、昨年12月に東京へお招きした滋賀県立河瀬中学校の皆さんとの「相互スタディツアー」の一環として、今度は私たちが滋賀県へ訪問させていただきました!
舞台となったのは、日本最大の湖、琵琶湖とその周辺地域。場所は滋賀県立河瀬中学校や、琵琶湖に浮かぶ日本で唯一の淡水島「沖島」など、まさに現場での体験を重視したユニークなスポットです。活動のきっかけは、生徒たちの純粋な「魚が好き」という想いから始まった河瀬中学校との交流でした。

この記事の続きはこちら→