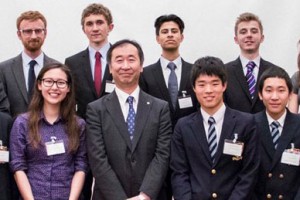夏休みが終わって9月も中旬を迎えるが、イギリスでは珍しく暖かな日が続く。この日も快晴、少し汗ばむくらいの陽気の中、中学部1年生と2年生は英語科フィールドワークに出かけた。
夏休みが終わって9月も中旬を迎えるが、イギリスでは珍しく暖かな日が続く。この日も快晴、少し汗ばむくらいの陽気の中、中学部1年生と2年生は英語科フィールドワークに出かけた。
目的地はGodalmingという町。1学期から定期的に何度もフィールドワークを行っているが、ここは今回が初めて。タイタニック号から最後のSOS信号を送り続けたというJohn George Phillipsの出生地。映画の撮影にも使われたという古い町並みが残る。が、何も知らなければ片田舎にあるのんびりとした平和な町である。
駐車場に2台のミニバスで到着すると早速先生方から諸注意があり、入念な打ち合わせが終わるとグループごとに町に繰り出していった。
本日の活動は10月末に開かれる本校の文化祭「OPEN DAY」のビラ配り。道行く人にチラシを渡すのだが、勿論、街頭でただただチラシやポケットティシューを配るのとは訳が違う。チラシを手渡すのはあくまで「きっかけ」。そこから何とか会話を始めるのが今回のミッションだ。
中1の生徒がまだ英語を習いたての先学期は沢山のイギリス人の中を歩き回るだけでも緊張していたのに、彼らも既に英語で「話しかける」ことには慣れてきた。先学期末はお店の中に入って簡単な質問を英語でしてみたが、今回は歩いている人に立ち止まってもらって話しかけることにも挑戦。ハードルを一つ高くしてみた。
前の授業で習った文章をノートに書き留め、目的地に到着するまでミニバスの中でもお経を唱えるように一生懸命練習した。この英語がどこまで通じるか… 緊張で始まったフィールドワークだったが、5分、10分と経つうちにしっかりと楽しめるようになっていた。
ポカポカと暖かな日。気持ちのいい陽気も手伝って、話しかける方も、話しかけられる方もいい気分でいられたのかも知れない。
「先生、この町の人って、みんなすごく親切!」
「あっ!あの人さっきインタビューした人!先生、あの女の人!」
恥ずかしいくらいの大声で嬉しそうに言う女子生徒の指差す方を見ると、ご年配の女性が微笑み返してくれた。
ガラス張りの不動産屋のお店に果敢に乗り込む中1男子、ちょっと怖そうなパンク風の若い女性たちに話しかける女子の班、車椅子のご老人に優しく声をかけた男子生徒もいた。町のあちこちで本校の中学生が地元の人たちと話をする風景を見るのはまた格別であった。
その話の内容はと言えば…
「とっても楽しいオープンデーがあるから是非来てください!ラジウィックという村の近くにある日本人学校です。私たち英語の練習をしているのですが、私の英語はどうですか?できればここにコメントを書いてください!」
そう言って、用意しておいたコメント記入用紙を渡して書いてもらう。これが先生に見せる「話した証拠」になるわけだ。
1つコメントをもらえれば1ポイント。制限時間内にどれだけコメントをもらえるか競いましょう! ポイントをたくさん稼いだ人たちにはご褒美がありますよ!
残り約10分。ご褒美目当てで始めたインタビューは、いつの間にか別の目的で続けられていた。
「さぁ、そろそろ時間ですから集合場所に戻り始めてくださいね。」
「もう終わりですか? もうちょっと聞いていいですか? 今度は僕の番! インタビュー用紙かして!」
「いや、今度は僕だよ。あと一人、先生、いい?!」
こんなことになるならインタビュー用紙は一人ひとり分けて用意しておけばよかった。他の班でも用紙の取り合いが…
困ってしまったが、これだけ積極的に話しかけられるようになったのは嬉しい限り… もはや彼らは「ご褒美」のためではなく、「英語を使える面白さ」のために躍起になって道行く人を探していた。
「ごめんね、また今度の機会に頑張りましょう。とりあえずミニバスの方に戻りますよ!」
人数を確認しながらふと通りの向こうに目をやると、10分以上も前に車椅子の人に話しかけた中1の男子がまだおじさんとお話をしていた。これには少しビックリ。まだ英語がおぼつかない中学校1年生がこんなに長い間お話をすることができるなんて…
「Hi, Sorry, but we should leave now… 」
車椅子の男性に声をかけると、大きなジェスチャーで嬉しそうに答えてくれた。
「Your student? He’s very good! very polite! Good boy!!!」
そこにさっき女子グループがインタビューをしたおばさんが通りかかった。
「先生!あの人、さっきインタビューした人!」
軽く挨拶をすると、こちらにやってきて、
「あなたの学校の生徒達? みんないい子ね。立教でしょ? 私、何十年も前に実はあなたの学校の制服を作っていたの!」
こんな会話をしている間にいつの間にか中1の生徒達が集まってきたのでみんなで記念撮影をすることにした。
「いいですかー!One two, and three!」
いい天気、いい笑顔、いい写真が撮れました。
 夏。28度、いや、それ以上かも分からない。とにかく暑い。イギリスなのに。そんな愚痴を吐く。朝からしていた勉強も集中が切れてしまった。一休みと団扇片手に空を眺めた。ふと気付く。そういえばイギリスで過ごす夏はこれが最後なのだと。あぁ、もう4年目になっていたのか。
夏。28度、いや、それ以上かも分からない。とにかく暑い。イギリスなのに。そんな愚痴を吐く。朝からしていた勉強も集中が切れてしまった。一休みと団扇片手に空を眺めた。ふと気付く。そういえばイギリスで過ごす夏はこれが最後なのだと。あぁ、もう4年目になっていたのか。