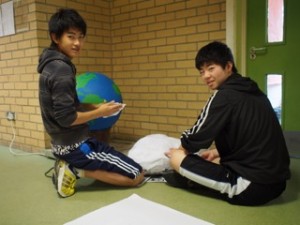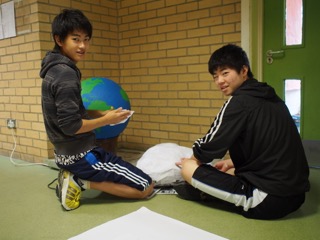先週の火曜日、女子バスケットボール部は新チームで初めての試合を行いました。対戦相手はBEDE’S。昨年度は2試合行い、一勝一敗という対戦結果でした。今回の試合会場となる相手校までは、ミニバスに乗って1時間以上の長い道のり。バスに乗った生徒たちは緊張の中、きれいな夕日や、勢いよく車道脇の草原を走り抜ける馬、牧場の羊たちなどイギリスらしい風景を楽しむこともできました。
1ピリオド、コートに入った選手たちからは緊張の様子が強く伝わってきます。今回初めて立教英国学院のユニフォームを着て、初めて現地の生徒と試合をする選手もいます。緊張は当然のことでしょう。最初に得点を決めたのは、本校。その後相手に4点決められましたが、1ピリオド終了時には6対4でリード。その後、2ピリオド13対12、3ピリオド27対23と接戦ながらも本校がリードを守っていました。しかし、4ピリオド終了時、スコアを見ると35対35。同点。3分の延長となりました。
新チームになってから人数が決して多くない中で上級生を中心に一生懸命に練習してきたこと、試合中に相手の隙や自分たちのプレーを学年を越えお互いに指摘する姿、この試合に勝ちたい思いは十分に伝わってきます。しかし、試合に勝ちたい気持ちは相手チームも同じです。延長では両チームともシュートが決まりません…。両者譲らない接戦の中、最初にシュートを決めたのは立教英国学院の生徒でした。その後も油断せず、落ち着いて合計6点を決めることができました。結果は41対35、立教英国学院の勝利です。
試合後は相手選手と、”How do you say thank you in Japanese?” 「ありがとう」とお互いの健闘をたたえ感謝を伝え合う姿がありました。現地の学校との試合は国際交流の機会でもあります。3学期も同校と試合を行います。次回は本校を会場とするので、たくさんの立教生に女子バスケットボール部のチームワーク、活躍を見せられるといいですね。