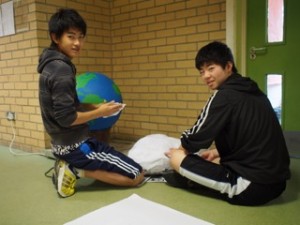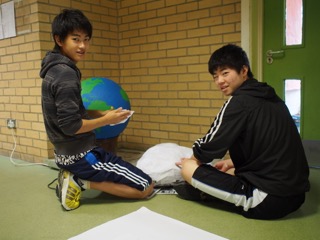爪についていた色とりどりのペンキも、すっかりきれいになり、準備期間中はこの洗っても消えてくれないペンキたちにムカついていたが、こうやってきれいになった手を眺めているとなんだか寂しい今日この頃。
私の文章力では伝えきれないほど、本当にたくさんの感動が詰まったオープンデイだった。クラス企画に劇企画… 色々なことが毎日のように起こったけれど、振り返るとどれも良い思い出となっている。
「命」について考えるテーマだった高2ー1のクラス企画。重いテーマだったがために、クラスでは皆で何時間も話し合った。どのテーマをとっても、答えがあるのかもわからない難しいテーマだったが、それぞれのグループがきちんと意見をまとめ上げていたのは、さすが高2。高1では無理だったと思う。賞よりも「伝える」ということを意識してやってきたお陰か、当日は、受付をしていると大勢のお客様から、「すごいね、」「考えさせられたよ。」など、沢山の声を頂いた。頑張って良かったな、… その時に一番強くそう思った。
最後のクラス企画、何より楽しめて良かった。そして、ずっとクラスを支えてくれた学級委員の2人に感謝したい。2人とも、ありがとう!
来年のオープンデイまであと1年。高3になっている訳だが、またうずうずしながらオープンデイを待つことにする。
(高等部2年生 女子)