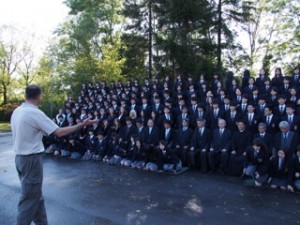私はこの夏ケンブリッジ大学で行われた一週間のサイエンスワークショップに参加しました。このワークショップは、英国人と日本人の高校生が一つのプロジェクトに配属され、いろいろな交流をしつつ、科学の楽しさや知恵を共有しあうプログラムでした。
私は英語が得意なので、私の英語力が生かされるサイエンスコミュニケーションというプロジェクトに入りました。サイエンスコミュニケーションとは、日常生活で科学に関わっていなかったり、科学を専門分野としていない一般の人達に、科学を理解してもらえるように、分かりやすく説明して、最先端科学を社会に伝えるものです。今回の私のプロジェクトの目的は、ワークショップで行なわれている他の三つのプロジェクトについてポッドキャストを作ることでした。ポッドキャストとはインターネットにアップロードされていつでも再生できるものです。
私のプロジェクトの指導者は、ハナさんという名の、naked scientistというケンブリッジ大学でサイエンスコミニケーションを主に活動しているグループの方でした。ワークショップの初日には生物学者が集まる脳とうつ病に関しての研究発表会に連れて行ってもらいました。最初はなぜここに連れて来られたか理解出来ませんでしたが、すぐにこの発表会がサイエンスコミュニケーションの第一歩であることに気付きました。なぜなら、この発表会には研究者本人がその場にいて、実際に質問や疑問に応じてくれるのです。私もファシリエーターの助けをかりて、気になる展示の説明を研究者から直接聞きました。私みたいな素人でも、とても丁寧に優しく説明してくれました。そして、その内容を理解したとき凄い喜びを感じ、授業では習わない科学の楽しさに触れることができました。これこそが科学を通してのコミュニケーションだと、私はその瞬間思いました。
その後は、プロジェクトのメンバー全員で集まってポッドキャストをどのような形式にすれば分かりやすいかを話し合いました。その結果、何について話しているのかが分かりやすいインタビュー形式にすることを決めました。次の日、早速他のプロジェクトの研究室に行き、インタビューをレコーディングしました。プロジェクトの研究室が一つ一つ雰囲気が違って、新しい研究室に入るたび新鮮でした。各々の研究室から、科学という一つの言葉にどれだけ様々な分野があって、世界を良くしようと研究が進められているのかがよく感じられました。
プロジェクトの最後は、レコーディングを編集する日でした。パソコンが余り使えない私には辛かったです。それでも、機械音痴の私でも編集の技術には驚かされました。誰でも話しているときは、「えっと、」や「えー」などと言ってしまい、話が途切れて余り良いスピーチに聞こえないときでも、編集の際、そのような語をカットし、よりスムーズに話しているように聞こえ、編集後にはどれだけ話すのがへたくそな人でも、上手に聞こえてしまうのです。ですが、この作業はとても時間と手間がかかり、パソコンが得意なパートナーの子にとてもお世話になりました。そして、最後の最後に自分が作ったオリジナルのポッドキャストに音楽を加え、ケンブリッジ大学のnaked scientistのホームページに載せました。
このプロジェクトを通して、他のグループの研究内容やその学問を深める目的を知り、そして科学の重要性と科学を通してもっと便利で安心できる未来がある事を知り、この自分が知り始めたばかりの科学の世界を皆と共有してより良い世界へと繋げたいと思いました。また、自分が作ったポッドキャストを、今世界中の人が聞けると思えば、不思議と自分が少し誇らしく思えて来ました。
サイエンスワークショップと名づけられているものだから、学問的なことばかりかと思っていたのですが、どちらかと言うと身近で実践的な内容で、想像以上に楽しかったです。このワークショップを通して最も自分が得たものは、科学の重要性に気づかされた事です。文系である私は、理系の人と比べて普段科学には無縁ですが、科学が苦手でよく分からない、学ぶ必要がないと言う人たちに、科学の楽しさと大切さを伝えたいと思いました。内容は全て理解し切れなくても、科学がどうやって私たちの生活を作り上げて来たか、私たちの日常生活や病院での設備をもっと良い物にするために研究者が毎日頑張っているということ、他人事のように思わず、皆に知ってもらいたいと思いました。
(高等部2年生 女子)