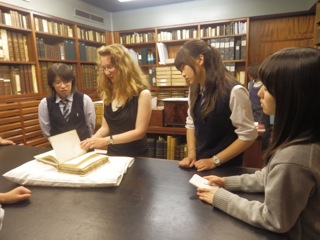Briefing weekend とは、サイエンスワークショップへの準備として立教で行われた交流会だ。いくつかの現地校から、合わせて20人ほどの英国人の生徒が来て、そこに立教生7人も加わり、3日間共に過ごした。一緒に食事をとり、寮も英国の女の子と同じで、普段立教生としか過ごさない立教で、英国の子と生活していることが不思議に感じられ、緊張した。
このBriefing weekendで立教に来た生徒達は、この後ワークショップで東北に行くためか、日本に興味を持っていて、とても気さくに話しかけてくれた。これまで交流した子達の中で最もフレンドリーだったため、多く話せて嬉しかった。
そうして会話する中で学んだことは、英語での会話で私に必要なものだ。
1つ目はあせらないこと。実際英国の人と話してみると、使う英語のほとんどはもうすでに文法上は習い、十分理解できるものであることに気付く。しかし、外国の人を前にすると緊張してしまい、分かる英語も分からなくなってしまう。落ち着いてよく聞くと、理解できると思った。2つ目は細かいところで気を抜かないこと。1つ目と共通するが、いざ聞き取って今度は自分が話すときに、焦りから3人称のsを忘れたり、aやtheを抜かしたり、過去形や未来形を間違えてしまったりする。そのような細かいところを正しく話そうと思った。
そして最も大事だと思った3つ目は、話を続けることだ。これは英語でなくても、全ての会話に成り立つ。例えば「どこから来たの」と聞かれて、「日本」とだけ答えるのではなく、「日本の静岡で、ちょうど真ん中あたりに位置します。富士山がある県ですよ。」と、出来るだけ多くの情報を話す。すると会話は続き、楽しいものになる。私は日本語でも会話が続かないことが多いなと気付き、最近は普段から質問を自然に続けるよう気をつけている。「会話はキャッチボールだ」とECの先生がよく言われるが、そのように自分が受け取ったら、相手に返すものだと意識しながら会話したい。
この3つが私に必要なものだと思った。これらに気をつけてコミュニケーションしていこうと思う。
またこのBriefing weekendの期間には、東北の被災地について学んだり、原子力発電所について専門家の方からお話をうかがったりした。その中で、日本が大好きで住んだこともあるという英国人の夫妻が日本人について話をしてくださった。その夫妻は日本人は丁寧で、礼儀正しくて、優しいと日本にとても良い印象を持っているようだった。しかしあえて悪いところを聞くと、「個人で行動しないこと」と言われた。自分はどう思っているのかもっと大事にしてほしいそうだ。福島の事故についてもそうだが、例えば周りが福島産の食べ物を買っていないから、自分も買わないとか、政府に対して個人の意見を発さないことに驚いたらしい。確かに日本人に「あなたはどう思う?」と聞いてもすぐに答えが出てこないことが多い。集団での行動に慣れてしまって、自分がどうしたいのかはっきり分からないところが私達の悪いところだ。もっと自分の意見を持ち、発信する必要があると感じさせられた3日間だった。
(高等部2年生 女子)