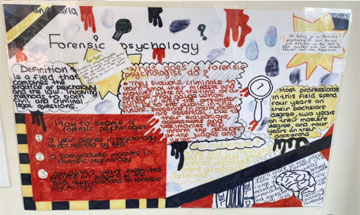5月1日(日)夕食後、全校生徒向けにCollyer’s College短期留学報告会を実施しました。
現高等部3年生6名が、2022年3月7日から11日までの1週間、Collyer’s Collegeに短期留学に行ったときのものです。報告会では、それぞれが履修した科目の内容を中心に現地での経験や、日本の教育との違いについて語ってくれました。発表後には在校生との質疑応答を実施し、予定していた時間を過ぎてしまうほど、双方にとって大変充実した時間になりました。今後、最高学年として、進路実現に活かしてくれることを願っています。
以下、6回に分けて、生徒のレポートを掲載します。(5/6)
7/Mar/2022 (Mon)
今日は二時間目と三時間目があったので一時間目は図書室で自習をしていました。しかし、初日の緊張で自習できず、その時間は次の授業のクラスに下見に行ったり、単語帳見たとしても何も頭に入らずあっという間に二時間目を迎えました。授業が始まったら自己紹介も無く始まりぬるっと授業が始まりました。続きの授業に途中参加した形だったので内容を理解するまで時間がかかり、電子辞書とパワーポイントとノートの行ったり来たりの繰り返しでした。二時間目が終わりブレイクに入って、教室に残っているのは先生と一人の静かな男の子と私の三人でした。先生が一度出ていき二人になったときに喋りかけようと思い、勇気を振り絞ってHelloと言ったが、ガン無視。心がズタズタにやられました。けれども来たからには話しかけないとと思い先生に話しかけました。その時にバックに忍ばせていた日本のお菓子コアラのマーチを出して、食べてもらいその流れで静かな男の子にもあげて少しでしたがお話できました。そのような感じでブレイクが終わり三時間目が始まりました。言ってることは何となくわかるが、自分の意見が言えず言いたい単語が出てこないことがありました。そんな自分の問題点がわかり、少し気持ちが落ち込んでいましたが、授業が終わりみんなと集合してお疲れ様って言ってもらって仲間の大切さも感じました。お昼は感染の心配をしてお外で食べました。パスタをみんなと喋りながら食べるのは楽しかったです。その後はずっと図書館で今日扱った教科書を借りて頑張って取っていたノートを復習したり、英語の勉強をしました。
濃いようであっという間に過ぎた一日でした。明日は一時間目から連続で授業があり、授業と授業の間の放課がないので焦る気持ち且つ、迷子になりそうで怖いという気持ちでいっぱいで寝れるかわかりませんが、楽しみたいです。
8/Mar/2022 (Tue)
Collyer’s College二日目。やはり緊張はすごかったです。朝タクシーに乗るときから口から心臓が出るんじゃないかってほど緊張して教室に入りました。そこには二人の女の子がいてどこに座るか戸惑っていたら一人の子が私の後ろが空いてると言ってくれてそこに座りました。後から来たその子のお友達と三人でグループディスカッションをしました。ほんとに優しくてせっかく話を振ってくれたのにその時は何もアイデアが出ず、終了。あとから発表してるときに自分のアイデアがどんどん浮かんできて申し訳無さと後悔と悔しさで今日も気持ちが落ち込みました。明日こそ、話します。二時間目、犯罪学。興味だけでとったのでどのようなものかドキドキとワクワクでした。初めに先生に挨拶したところクラスの子に自己紹介してくださり、とても良い雰囲気で授業が始まりました。嬉しかったです。心理的な犯罪学のTheoryや社会的な犯罪学のTheoryから学びました。初めての科目だったので新鮮で楽しかったです。
二回目のブレイクになりました。前回のように教室にいるのが、私一人と男の子だけなので話しかけたいと思い、けれどもその子はゲームをしていました。昨日のトラウマがありますが、勇気を振り絞って、コアラのマーチを片手にHello。なんと返してくれました!!そのまま犯罪学を選択している人はどのような職業につくのか質問したり、ほかには何の科目をとっているのか、またその子のアクセントがなまっていたのでどこの出身なのか聞いたりしました。喋るかけて良かったなと思いました!三時間目は英国の犯罪が起こる理由の一部について考え学び、映像や図を実際にみて日本じゃこうはならないだろうなという部分があったのでとても印象的でしたし、興味深かったです。
そのあとはランチを食べて、ずっと図書室で今日やったことを復習しました。コリアの図書室はきれいで教科書もおしゃれなのでモチベーションが上がりあっという間に時間が過ぎました。明日も話しかけて得られるものをたくさん得たいです。
9/Mar/2022 (Wed)
今日は朝から犯罪学があって、初めは昨日の復習から始まって先生が出した質問の答えがノートに書いてあったのに勇気が無く言えず心の中で唱えていました。答えがやはり自分が思っていたものでそれがわかった瞬間にああああってなって発言すればよかったと後悔でいっぱいでした。そんな悲しい気持ちで一時間目が終わり、残る授業は心理学の二時間で最後の心理学でした。話しかけてもらって仲良くなった子たちとなんとしてでも写真を撮ってインスタを交換すると決めました。10分前に行って心の余裕を持ちながら待っていました。前回の授業の最後に課題のようなものが出されたのでそれをやっていて、あっているか見てほしいとお願いしてそこからなんと先生が、前まで私は一人で座っていましたが、横にその仲いい子を座らせてくれて二人で話せる機会を作ってくれました。こうなったらもう私の勝ちです。友達の勉強を邪魔しないようにしながらも積極的に喋りました。二人で話し合う時間のとき自分の意見をがんばって出して話して最後に時間が余ったときもくだらないことかもしれないけど喋って、インスタ持ってる?交換したい!!と言いました。OKしてくれて交換できました。
一度お昼休憩があり離れてみんなとご飯を食べていると竹内さんのお友達の人が声をかけてくださって喋って、インスタ交換して、写真を撮りました。そんな楽しいランチが終わり、心理学をもう一時間受けました。楽しく受けることができてあっという間に授業が終わってしまいました。帰りに仲良くしてくれた子達と写真撮って別れを告げました。今日になって凄い仲良くなれたのに今日お別れしないといけないのが悲しくてそれなのにみんな優しくてフライト無事にできること日本につくこと祈ってるねと言ってくれたりもう本当に心が暖かくて涙が出ました。まだこれからも会いたかったけど無理なのでインスタで連絡するねといって今日が終わりました。
仲良くなって気づいたことはみんな自分のことを恥じていないことです。発言のときも思ったことはすぐ手をあげて間違ったとしても恥ずかしいと思わずにそして写真を撮ったときには私達可愛い〜!!!と連呼してました。とても面白かったですし、そうすることで一日一日が明るくなるなと思いました。新しい気づきと自信がつきました。
今日はほんとに楽しくて友達ができて、the留学ということを感じることができました。明日は何があるんでしょうか!?!とても楽しみです。
10/Mar/2022 (Thu)
今日は2科目だけで、残りは図書館で過ごしました。コリアでの生活に慣れたと思います。犯罪学は今日が最後でした。最後だったから何か特別なことがあったという訳ではありません、普通に前で男の子たちがペン投げて笑ってたり、tiktokを見過ぎてるだとかたわいもない会話をしてて親近感が湧きました。勝手に私たちのような高校生ではないんだろうなと思っていたけれどあまり変わらず、微笑ましかったです。しかし最後授業が終わって教室を出るときに一人のクラスの男の子が「今週帰るの?」とわざわざ話しかけてくれて、もちろん驚きましたが嬉しくて色々笑顔で話せました。インスタ交換もできてその後の自習時間でも会話できて本当にコミュニケーション力、積極性が初日と比べて変わったなと思いました。昨日に引き続き友達が増えて非常に嬉しかったです。
そして今日の夜は焼き餃子パーティーでした!初めての立教での焼き餃子、美味しかったです。少人数だったのでまるで本当に大家族でご飯を食べてるようでした。温かい気持ちになりました。
明日も誰かと話して笑って仲良くなれるかも?と夢を見て、ドキドキ楽しみながら、最終日を過ごしたいです!
11/Mar/2022 (Fri)
Collyer’s最終日。ここまで今思うとあっと言う間でした。今日は最終日にして初めて英語の授業がありました。そこではイギリスのスラングと基礎の歴史を学びました。現地の人が使うと思う、ある程度知った方がいいと思うものが学べてこれは役に立つなと思いましたし、ここならではの学びなので授業を受けれて嬉しかったです。ラストの社会学では前に仲良くなった子のお友達がいてその子から話しかけてもらい、自然と笑顔になりましたし、すごく私にとって何故か話しやすかったので自分の紹介に加えて、日本の印象とか何の芸能人が好きかなど、たわいもない会話でしたけど、楽しく話しました。Collyer’sにいる人は優しい人ばかりですし、昨日夢に見てたことが叶って嬉しかったです!
最終日にホーシャムで少しお買い物をする時間を作ってくださり放課後にお出かけをしました。雨が降っていたのですがそんなことをポジティブに捉えて信号機を渡るのでさえ、公園を歩くのでさえなんだか楽しかったです。先生がいない、携帯も使えないなか地図だけをもとにショッピングモールに行って食べ物を買ったり、雑貨を買ったりOutingより全然時間がないし行けるところも少ししかなかったのにすごくCollyer’s組と行くのが新鮮で、終始笑顔で特別な思い出になりました。
五日間という期間で色んな景色をみて、真似してみたり、挑戦したり、自分の出来なさに落ち込んだり、悩んだり、自分の些細な変化に嬉しい気持ちになったりしました。そして私とCollyer’s子達の違い、そして気づく点が多々ありました。これらはこの短期留学に参加したからこそ感じたことで自分にとって成長になりました。この機会に参加したからといって今すぐ自分が大きく変化したり、英語力が格段と上がったわけではありません。しかし、自身を大きく成長するにあたっての特別なポイントになることは確かです。これらを大学や将来の自分の生活、そこでの周りとの共存に活用したいと思います。このCollyer’s Collgeでの短期留学に参加して本当に良かったです!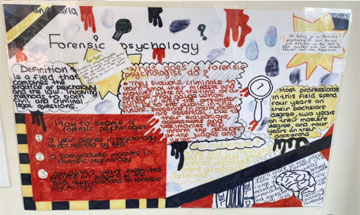
 するその時、ブザーが鳴り試合が終わった。私は負けたと思っていた。点数表を見ると、3点差のついている数字でアドバンテージをとっているのは自分たちのチームだった。その時私は涙は出なかった。汗で体の水分が持って行かれたのだろう。試合終了の礼をし、相手チームの選手、チームメイトとともに歓喜する。これがスポーツの力なのだと知った…。
するその時、ブザーが鳴り試合が終わった。私は負けたと思っていた。点数表を見ると、3点差のついている数字でアドバンテージをとっているのは自分たちのチームだった。その時私は涙は出なかった。汗で体の水分が持って行かれたのだろう。試合終了の礼をし、相手チームの選手、チームメイトとともに歓喜する。これがスポーツの力なのだと知った…。