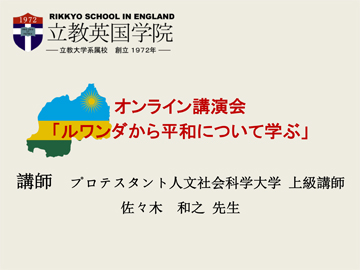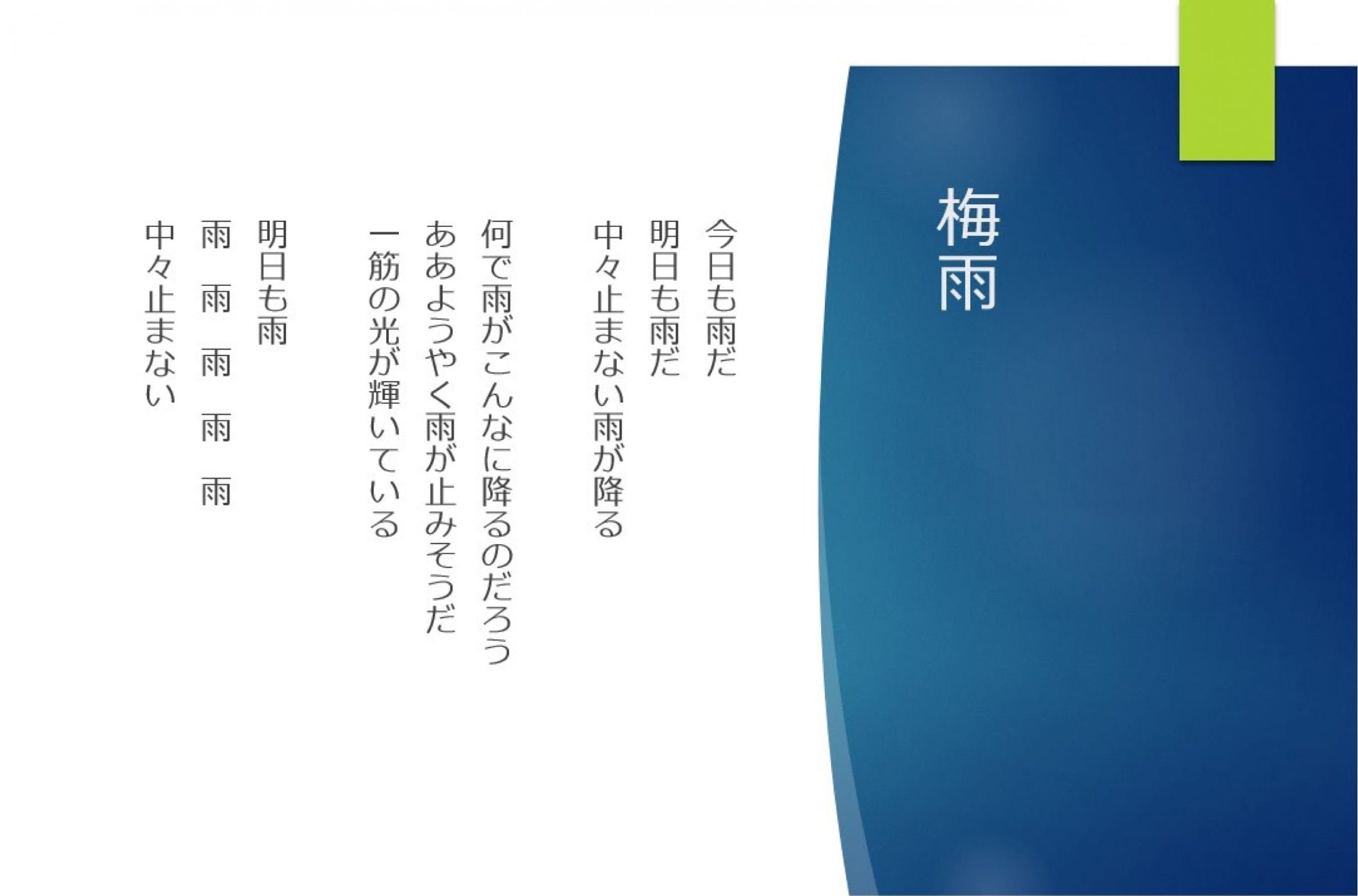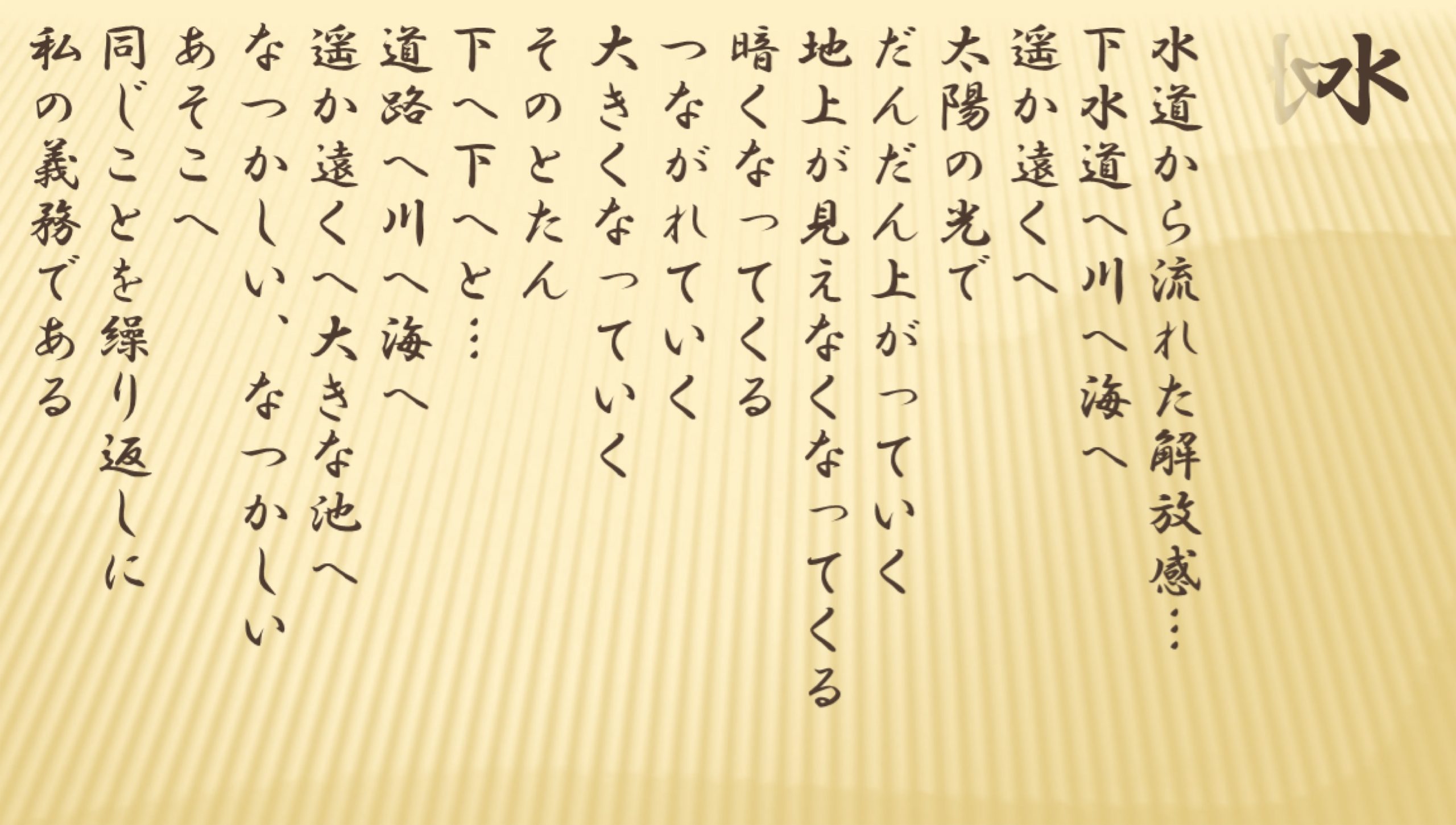中3国語では1か月近い期間を使い、「コロナ禍と社会について考える」という単元を行いま した。生徒個々人の頑張りは勿論、月曜のオンライン学習で課題文を読んだ後Googleフォームで振り返り・質問への回答、木曜のインタラクティブ授業で読解内容の確認と交流という形で進められたからこそ出来た学習です。今回は、学びをまとめるために各自で問いを立てて文章を書くということをしてもらいました。今後も彼らは答えの明確に出せない問いと格闘しながら考え続けてくれることでしょう。授業担当として大いに期待しています。
した。生徒個々人の頑張りは勿論、月曜のオンライン学習で課題文を読んだ後Googleフォームで振り返り・質問への回答、木曜のインタラクティブ授業で読解内容の確認と交流という形で進められたからこそ出来た学習です。今回は、学びをまとめるために各自で問いを立てて文章を書くということをしてもらいました。今後も彼らは答えの明確に出せない問いと格闘しながら考え続けてくれることでしょう。授業担当として大いに期待しています。
生徒の書き上げた文章を3回に分けてご紹介します。今回は下記3点です。
* * *
コロナ禍の社会とペストについてのまとめ
私が今回のまとめの文章の中でとりあげようとしている問いは、「物語の主要な登場人物は最終的に何を目指しているのか」ということである。『ペスト』の小説自体が難しかったので自分なりの解釈で話をまとめようと思う。私が説明するのは、リウー、コタール、ランベールの三人で、それぞれの立場から考える。まず、コタールは、犯罪歴のある男で逮捕されることに恐怖心を抱いていたが、ペストによる混乱の中で人々が恐怖しているのを見て、おびえているのは自分だけでないと感じている。そのためペストの混乱に安心感をいだいておりこの混乱がおさまることを望んではいない。
ランベールはパリに住む新聞記者だが、ペストが流行するオラン市に閉じ込められてしまう。妻が待つパリへ帰るため脱走をこころみる。だが最終的に、リウーも妻と離ればなれになっていることをきかされ、リウーに協力を申し出る。リウーは決して名医ではない。ペストをくいとめられるわけではないが、死にそうな患者の手当てからにげない立派な医者であり、ペストがはやく終息することを願っている。こうして登場人物それぞれの想いを見ていくと、人間の薄汚さや生きることの本質が分かりやすいような気がする。それは現代社会でも同じで、ほとんどの人がリウーのように終息を願うが、中にはコタールと同様に混乱が心地良いと感じる人もいるのだろう。しかしやはりコロナは乗り越えていくべき壁だと思う。医療従事者の方をはじめとし一人ひとりの意識によってコロナが一刻もはやく終息することを願う。
* * *
漫画『ジョジョの奇妙な冒険』とともに考える正義
まず前提として、このまとめ文章は僕の思うことをまとめたものです。不確かなことを事実として断定したり、僕の考えを押し付けようとしたりするつもりはないことを理解していただきますよう、よろしくお願いします。
はじめに
今回の国語の授業内で小説『ペスト』の一部を読んで、僕は正義について疑問が生まれました。正義とは何なのか?は人によって違うものだと思います。二つの違う正義感を持った人物が対立したときどうするのが正しいのか?という疑問です。しかし、この小説『ペスト』は僕にとっては少し難しい内容の物でした。なので、このペストを読んで生まれた疑問について、何とか思考するために他の資料を用意しました。その資料とは!漫画です。資料として出させていただく漫画は『ジョジョの奇妙な冒険』という作品で作者は荒木飛呂彦先生です。なので、このまとめ文では僕の好きな人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』とともに正義について考えていきたいと思います。
『ジョジョの奇妙な冒険』とは?
まず、『ジョジョの奇妙な冒険』とともに正義について考えるにあたって、漫画『ジョジョの奇妙な冒険』についての基礎知識が必要だと思います。なので、大体の登場人物や、その性格、人間関係、などを書いておきます。大体知っている人は読まなくてもいいと思うので、次の題名まで飛ばしてください。まず、このまとめ文では『ジョジョの奇妙な冒険』、通称『ジョジョ』(今後は『ジョジョ』と表記します)の数あるシリーズの中でもその原点である『ジョジョ‐第一部ファントムブラッド』の少年期にしぼって考察をしていきたいと思います。
「この物語はある2人の若者と、血塗られた伝説を持つ古代アステカの石仮面にまつわる奇妙な物語である。」‐ジョジョ ファントムブラッド冒頭。この作品の舞台は立教英国学院ができる前の時代、1889年のイギリス。主人公はジョナサン・ジョースター(今後はジョナサンと表記します)で、周りのみんなから名前に「ジョ」が二つ付いていることから、ジョジョと呼ばれています。父は名門貴族ジョージ・ジョースター卿で、かなり裕福な家庭で育っています。ジョナサンは正義感が強く第一話の登場シーンでは、からかわれている少女を助けるために少女をからかっている男たちに殴り掛かかっています。一見かっこいい正義のヒーローに見えますが、その直後にその男たちにボコボコにされています。このことから、ジョナサンは勝てないケンカにでも、自分の正義感を信じ貫き、正しいと思ったことを行動に移す性格だという事がわかります。ジョナサンは立派な紳士を目指していますが、少女を守れても、ケンカには勝てなかったり、テーブルマナーがなかなか身につかなかったりと、あまりとんとん拍子にうまくいっているわけではありません。なので、一言でいうとジョナサンは「真面目だけど不器用」な性格なのです。
対して、この物語のいわゆる悪役として登場するのがディオ・ブランドー。彼はイギリスの貧民街の出身で、彼の父、ダリオ・ブランドーの死をきっかけにジョージ・ジョースター卿の養子になります。彼は、悪役でありながら、非常に利口で器用です。しかし、その行動理念はいたって単純かつ欲望的で、自分が一番でありたいというたったそれだけです。しかし、その単純な欲望のためなら何でもするのが彼の恐ろしいところでもあります。その証拠に彼はあるシーンではジョナサンに向かって「いいか!ジョジョ最初に言っておく!これから君の家にやっかいになるからといって僕にイバったりするなよな。ぼくは一番が好きだ。ナンバー1だ!誰だろうとぼくの前でイバらせはしないッ!」と言っています。このセリフだけならまだかわいいものですが、彼の性格はその行動にも出ており、かなり序盤の方で「犬の人間にへーこらする態度が気に入らない」という理由でジョナサンの愛犬ダニーを焼き殺しています。同じ十四歳の行動とは思えません。
一見、彼は自己中な奴だとみんなに嫌われそうにも思えますが、彼のカリスマ性にたくさんの人が惹かれています。ディオの取り巻きのひとりが「さすがディオ!俺たちにできないことを平然とやってのけるッそこにシビれる!あこがれるゥ!」と言っています。ディオは一言でいうと「悪のカリスマ」って感じですかね。
他にもたくさんの登場人物がいますが、今回はこの対照的な二人で悪と正義について考えていきたいと思います。
やっと本編
上のキャラクター説明ではジョナサンとディオの二人は対照的だといいました。では二人には共通点はなく、ディオが悪役だと決まっているのでしょうか?
二人にも共通点はあると思います。二人とも、他人に流されずに、自分の意見をしっかりと持っていて、なおかつ行動派であるという事です。ジョナサンは確かに人気キャラクターです。彼のまっすぐな部分は多くの人にとって正義感が強い少年に見えるでしょう。しかし、ディオも人気キャラであることは確かです。ときどき僕も彼のカリスマ性にはとても惹かれることがあります。悪行を働いている悪のカリスマでさえ、魅力的に見えることは少なからずあるという事です。では、その人は、この例でいうとディオは悪行を働いているから人気キャラなのでしょうか?
僕は一概にそうとは言えないと思います。確かに、すがすがしいほどに欲望的で、一瞬の迷いもなく極められた悪というのは多くの人が「かっこいい!」と感じさせられるものがあるのかもしれません。しかし、ディオの行動がすべての人にとって悪行なのでしょうか?例えば、上の『ジョジョの奇妙な冒険』とは?の中で、ディオの取り巻きの例を挙げました。取り巻きはディオの行動を見て「さすがディオ!俺たちにできないことを平然とやってのけるッそこにシビれる!あこがれるゥ!」と言っています。これは普通の人にはできない悪行をディオは平然とやってのけるので一種の「ワル」にあこがれる精神と似たようなものなのでは?と思う人もいるかもしれません。しかし本当にそうなのでしょうか?人によって正義感が違うという話はよく聞いたことがあると思います。しかし、ディオのよう悪を極めた存在にとって、正義感がどうだとかはどうでもいいのではないでしょうか?自分がやっていることが正しいのか?なんて考えていたらディオはダニーを焼き殺せたでしょうか?おそらくですが、彼の場合、彼自身がやっていることが悪行だと理解していると思います。少なくとも、他人に配慮した善行ではないという事は十分に理解しているはずです。しかし、ディオの取り巻きにとってディオの行動は正義だったのかもしれません。
つまり何が言いたいかというと、正義感は人それぞれで、行動を起こしている人にとってその行動が悪だったとしても、それを見た人が正義だと思えばその人にとってはその行動が正義だという事です。
まとめ
ここからは少し強引にまとめていきます。
最初の問い、二つの違う正義感を持った人物が対立したときどうするのが正しいのか?に対しての答えを考えていきたいと思います。まずこれに対しての答えは断定はできません。しかし、僕が思ったことは対立したのが二人だった場合は、たくさんの周りの意見が必要だと思いました。片方にだけ肩入れするのではなく、両方肯定派、片方肯定派、両方否定派などたくさんの意見を持った人たちと話し合うことで、状況はかなり変わるということです。状況を解決するのではなく解決を目指して改善していく事が大事だと思います。お互いを尊重し、なおかつ各々が自己主張をする。そういう世界にできたらいいなと思います。
* * *
コロナ禍の中で、私の立場なりに出来ることは何だろうか
私は、コロナ禍が私自身に大きな影響を与えたか、というと実のところあまり実感が湧かない。今もこうして変わらず勉強したりテレビを見たり、美味しいご飯も食べられたりと、何不自由なく日々生活を送っている。つまり、コロナ禍による外出禁止といえども、私はそこまで事の重大さを理解できずに、のほほんとその命令に従うだけであったように思う。コロナは、私と近いようで遠い存在なのだ。
そんな中で私は、国語の授業で『ペスト』という本と出会った。この本は、感染症が生活の中に降りかかってきた時の人々の様子が描かれていて、今のコロナの状況と重ね合わせると、ふと気付かされることがたくさんある。授業では、この物語の部分的なところしか扱わなかったけれど、その中で私が強く感じたことがある。それは、「深い」ということだ。
テレビなどで注目視されるのは偉い人であったり、特別にすごい人であったりと、社会の明るい、見える部分が多い。しかしペストには、医師、観察者兼記録者、新聞記者、凡人や悪役的な立場の者など、幅広いキャラクターが登場する。そしてその凡人であったり、悪役的な立場の人間にも、スポットライトが当てられているのだ。善は善、悪は悪、といった見方ではなくて、本当にいろんな人の意見を交えた内容になっている。
その意見のぶつかり合いの中で、印象深かった場面がある。新聞記者のランベールが、医師のリウーから保健隊に入らないかと誘われるがそれを断った場面だ。そしてその理由を、「僕はヒロイズムというものを信用しない」、「僕が心をひかれるのは、自分の愛するもののために生き、かつ死ぬということ」というふうに述べていた。私は、人助けの行為に反対するランベールに対して、どうして入らないのかという気持ちでいたが、彼には彼なりの理由があり、私もそれを悪いとは思わず、素直に納得できた。その答えに対して医師は、「今度のことはヒロイズムなどという問題じゃない」、ペストと戦う唯一の方法は、「誠実さ」であり、その誠実さというのは、「自分の職務を果たすこと」と述べている。リウーは医師という立場からして、社会の中ではヒーロー的な存在である。だからといって称賛するわけではないけれど、リウーの本質を理解した上での考えというか、その心意気は素晴らしいと思った。日々感染者が増加して疲労困憊する中、患者さんに対する同情の気持ちが消えつつも、医師として感染症と誠実に向き合う姿はとても尊敬した。
このように、善い行為に反する人がいけないとか、ヒーロー的な人だからすごいとかそういう問題ではないんだということを、私なりに理解した。感染症との戦いと立ち向かうのは、医療関係者や政府などの社会の見えるところに存在する者だけでなく、見えないところで過ごしている私のような学生や、大人たちであったりすることに変わりはない。そしてたくさんの人が自分の職務をまっとうしていることだろう。だから私も、私の立場なりに出来ることを精一杯まっとうしたいと思った。
授業で、あるひとりの看護師さんからの意見を知る機会があり、「何をしたらありがたいか?」というクラスメイトの中の誰かの質問があった。私は、マスク着用とか、三密を防ぐこととかを予想していたが、看護師さんは「みなさんの身近な医療者に応援のエールを送ってほしい」と回答された。それは、コロナと身近にいるからこその意見だと思う。そのような立場にいる人の意見や気持ちを知るということは、私みたいに感染症の重みを知らない人にとって物事を考えるきっかけとなり、ある意味私の「誠実さ」であるのではないかと感じた。この世の中には本当にたくさんの人がいて、たくさんの意見、考え、思いがあるのでこれが正解というのは分からない。また、自分が行動に移すだけで社会が変わるわけでもない。でも、自分なりに出来ることをまっとうするという「誠実さ」は、大事にするべきではないだろうか。そして、私は他人の意見を理解、尊重するとともに自分なりに深く考えられるようになりたい。