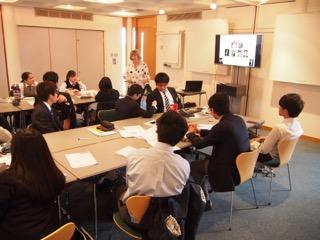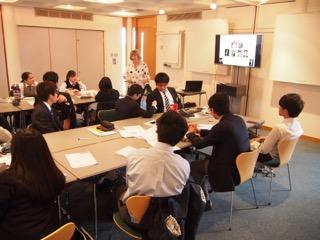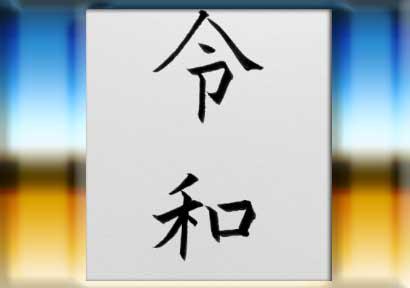ケンブリッジ研修も中盤を迎え、授業も本格的になってきました。5日目は、午後の美術館見学のためのレッスンを午前中にしっかりと行い、次の日のプレゼンテーションで発表するテーマが更に一つ付け加わりました。2つのチームに分かれて美術館を巡った後はセンターに戻って翌日のプレゼンテーションの準備。チームリーダーが上手くまとめて効率よく分担して作業にあたっていたようです。
やること盛り沢山の毎日で、この日は自習室が閉まる時間ギリギリまで熱心に準備に取り組んでいた生徒たちですが、実はその夜には大きなイベントがもう一つーーー「フォーマル・ディナー」がありました。ケンブリッジ大学の各カレッジでは定期的にフォーマルのディナーがあります。そのカレッジに属する人から誘われた人たちだけが参加出来るスペシャル・ディナーです。この日はマリー・エドワードカレッジのフォーマル・ディナーに本校の生徒達が招待されました。しかも今回は、普段はフェローと呼ばれる特別な方々が使う部屋でのディナー。ナイフとフォークを格好良く使える立教生はいつも通りに粛々と食事をしていましたが、背筋も更にしっかりと伸び、美食を堪能しながら、社交をすることが出来ました。
そして翌日はいよいよプレゼンテーション当日でした。2つのチームが2つのテーマについて順番で発表します。審査員は嘉悦センターの所長さんとそのご家族、レッスン担当の先生、そして学校から引率で参加している2人の先生の計6人。先ずは火曜日に訪れた Polar Museumで調べたことを発表、続いて昨日行ったFitzwilliam Museumで調べた古代ギリシャ・ローマをテーマにした発表でした。それぞれ約15分のプレゼンテーションは、切り口も資料も色々工夫してあり、短い時間の中でよくここまで準備が出来たものだと感心するばかり。。。とは言え、最初の発表は不慣れなこともあってか、少々声が小さかったり、原稿が棒読み気味であったり。。。すかさず、審査員の先生方からは、お褒めの言葉と共に様々なアドバイスも頂きました。もう少し声が大きいといいですね、顔をあげて聞いている人の方を見ましょう、「原稿を読む」のではなく伝える気持ちを大切に! … etc。彼ら彼女らの凄いのは、それを2つ目の発表ですぐに活かせたこと。原稿を暗記することはすぐには出来ませんでしたが、なんとか顔をあげるように努力をし、さっきよりずっと大きな声で話し、ちょっとしたミニ・ドラマ風の会話を入れたり、I think …とコメントをしたり。。。それだけでも見違えるようになったプレゼンテーションでした。きっとこれが彼ら彼女らの次なるプレゼンテーションへの自信に繋がるのだと思います。
午後は日本文化を学ぶセッションがありました。ここ嘉悦センターは日本文化発信の拠点でもあるようで、研修に参加している生徒達のために生け花・三味線・茶道の体験セッションを用意してくれました。3つのグループに分かれてそれぞれ2時間ほどの活動をしました。基本の花型=真副体(しん・そえ・たい)から丁寧に教えてくださった「生け花」セッションでは、最後には思い思いの自由体の作品を作ってホールに並べ、日本風の箱庭までついた立派な茶室でお茶を点てるところまで体験できた茶道セッションでは時間が経つのも忘れてお茶の先生方と歓談をし、そしてヨーロッパで活躍する津軽三味線の名手、一川響さんから直々に三味線の手ほどきを受けた生徒達はその日の夜のミニ・コンサートで一川さんと一緒に演奏できるほどまでに練習に励みました。イギリスの地で改めて日本文化に触れその良さを知ることは、イギリスの方々とのこれからの交流にきっと大いに役立つことと思います。
北海道出身の嘉悦センターのコックさんが腕によりを掛けて料理してくださった夕食、”北海道名物” 鮭のちゃんちゃん焼きを堪能した後は、センター内のホールで一川響さんの津軽三味線ミニ・コンサートがありました。一川さんはヨーロッパでただ一人のプロの津軽三味線奏者です。日本の伝統的楽器の素晴らしさをヨーロッパの人々に伝えるその音色にはどこかヨーロッパの響きが添えられているような、そんな新鮮な感動も味わえたコンサートでした。
1週間のハーフタームがいつの間にかこんなに充実した毎日になっていることに改めて気付いた2日間でした。