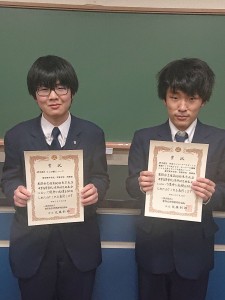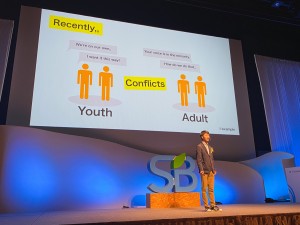- インタビューに受け答える生徒たち
- ミツバチの内検の様子
先般3月19日(金)に、みつばちプロジェクトが毎日新聞社の社会部の方から取材を受けました。取材では、4月から高2になる飯尾君、奥山君、土肥君が紙芝居形式でプレゼンをし、記者からの質問などにも答え、記者の女性から「深く考えて取り組んでいらっしゃる姿に驚きました。」と感想を頂きました。その後、実際に養蜂場のある屋上にご案内し、ミツバチの世話をしている様子もご覧いただきました。こちらの内容は、来週29日(月)発行の毎日新聞朝刊教育面に掲載される予定です。(※紙面事情で変更になる可能性もありますので、予めご了承ください)
【みつばちプロジェクト】毎日新聞の取材を受けました⇒コチラから