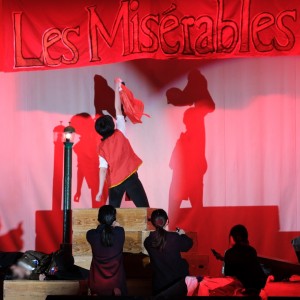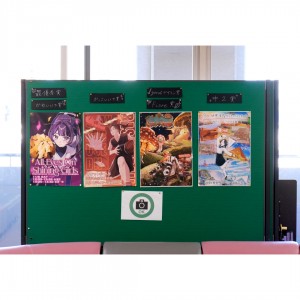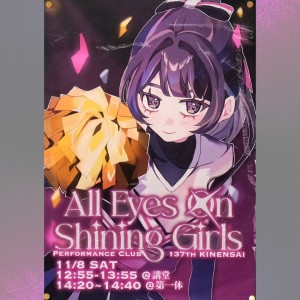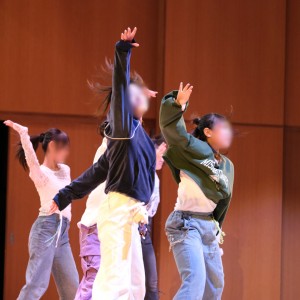【東京女学館中高 水泳部副部長 高2 M.T.】
今年の水泳部は、「大会で自己ベストを更新する」という目標のもと、日々の練習に力を入れてきました。厳しいメニューが多い中でも、互いに声を掛け合いながら励まし合い、多くの部員が大会で自己ベストを達成することができました。これは、一人一人の努力はもちろん、チーム全体で高め合ってきた成果だと感じています。
夏休みの合宿では、1日で10キロ以上泳ぐコースもあり、心身ともに大きな負荷がかかりました。決して楽ではありませんでしたが、部員同士が支え合い、最後までやり遂げることで、チームとしての結束もより強まったと感じています。
現在はプール練習を終え、陸上トレーニングを中心に活動しています。高校生は2月に最後の記録会を控えており、そこで良い結果を残せるよう、ここからさらに気を引き締めて練習に取り組んでいきたいと思っています。
部員全員が同じ目標に向かって協力し、まとまりのあるチームとして活動できた1年でした。来年も水泳部らしく努力を積み重ね、より良い成績と成長を目指して頑張っていきます。
【中3 Y.F.】
今年も大会での自己ベスト更新を目指して日々部活に励んできました。水泳部はタイムに応じて、5コースを最高レベルとして、段階ごとにコース分けされています。
私は中1のとき1コースで、2年間の特訓を続け、現在は4コースまで上がることができました。「もうタイムは伸ばせないだろうな」。モチベーションが低く始まった今年度でしたが、合宿でみんなと声をかけあい、話しているうちに、自分も今できるベストを尽くして頑張ろうとやる気が湧いてきて、合宿ではすべてのメニューに本気で取り組めました。結果、自己ベストを更新できて本当に嬉しかったです。
水泳部で友情を深めたり、大会で自己ベストを更新するために本気で頑張ったりと、かけがえのない経験を積めました。来年も水泳部で頑張りたいです。
【中2 Y.O.】
今年度の水泳部活動で最も力を入れたのは、夏の合宿と中体連の試合です。夏休みにあった合宿は、体力的にも精神的にも非常に厳しく、特に2日目は午前と午後で合計8km以上を泳ぎ込みました。そんな中、2日目の夜にあった花火の時間は友達とリラックスして過ごせる、合宿の中でも特に思い出深い時間となりました。そして、合宿の最後に行った記録会は、中体連への出場の可否に関わるため、泳ぐ直前は足が震えるほど緊張していました。最終日にはアイスを賭けてリレーを行い、チームで盛り上がりながら合宿を締めくくることができました。
中体連の試合では、自己ベストを更新できるかという、自分との戦いのようなプレッシャーが一番大変でした。緊張感の中で、自分の持っている力を最大限に発揮する難しさというものを痛感しました。
この厳しい経験を乗り越え、大きく成長できたと感じています。来年度も部員のみんなと共に楽しみながら、目標とする大会で自己ベストを更新していきたいです。