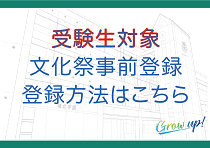中学サッカー部では、中体連第4支部選抜をはじめとして、選抜活動に参加している選手が各学年、複数名おります。
現中学3年生(U-15)
この学年からは、第4支部選抜(板橋区・北区・豊島区・文京区の代表)に3名選出
城北地区選抜(第4支部選抜+練馬区・中野区・杉並区の代表)に3名選出
その後、東京都選抜には1名選出していただきました。
この夏、伊藤 壮祐(いとう そうすけ)君、小島 悠暉(こじま ゆうき)君、松川 大志(まつかわ たいし)君が、8月1-3日に城北地区選抜の合宿に参加し、さらに松川君は同13-15日に行われた東京都選抜の合宿にも参加させていただきました。
この3人は、選抜活動を通して、人としてまたプレーヤーとして本当に多くのものを得て、大きく成長してくれています。

現中学2年生(U-14)
この学年からは、第4支部選抜に2名選出
城北地区選抜に2名選出していただきました。
この夏、中学3年生と同様に、藤井 葵斗(ふじい あおと)君、藤田 崇佑(ふじた そうすけ)君が、8月1-3日に城北地区選抜の合宿に参加させていただきました。
この2人には、その活動を通して得た経験をこれから始まる新人戦に大いに活かしてチームに貢献してもらいたいと思います。

中学1年生(U-13)の選抜の選考会はこれから始まります。本校のグランドも選抜活動の練習の場として提供させていただいておりますが、本校サッカー部の活動はもちろんのこと、選抜活動へのご理解とご協力をいただいております保護者の皆様、そしていつも選手に寄り添い、熱く指導してくださっている選抜スタッフの方々にこの場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございます。
(中学サッカー部顧問)