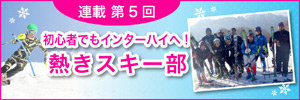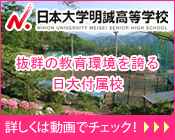運動部の黙祷
日大明誠高校に地震後の4回目の3.11がやってきました。
あの日と同じように青空が見え、梅の花が咲く明誠高校。あの日と同じように、試験後の学校で一般生徒は自宅学習。校内では吹奏楽部と野球部とバスケットボール部が活動しています。違っているのはあの日がもう過ぎてしまった事実だということ。今日は朝からテレビなどではあの日のことが繰り返し言及されています。本校でも、朝から本館前で弔旗を掲揚し、教職員朝礼で午後2時46分にはその時いる場所で黙祷を捧げましょうという申し合わせがありました。
第1運動場(人工芝グラウンド)で部活動をしていたサッカー部は、活動が午前中だということで、時間を早め黙祷を行うことを決め、午前中に、ラグビー部の生徒たちと共に黙祷をしました。黙祷の前には手塚先生から訓話がありました。午後2時46分には本校に放送が流れ、教職員、部活動の生徒が一斉に黙祷。野球場では練習を一時ストップして、黙祷を捧げた後、小口監督が震災のあった日のことを含め話をしていました。
あの日は、本校でも忘れられない1日となりました。危機管理という言葉が本校の教職員の中でも話題に上がるようになったのはそのときからです。あの日に本校が行った行動に関してはいろいろな意見を聞きますが、あの時にはできる限りのことをしたと今でも思っています。今では生徒全員が学校にとどまることになっても大丈夫なだけの毛布や水、非常食も用意されています。
午後2時46分。大きな揺れが明誠高校を襲います。最初は普通の地震だと思っていましたが、そうではないとすぐにわかりました。吹奏楽部の生徒たちが音楽室からグラウンドに降りてきます。幸い、校舎の損傷はほとんどありませんでした。地震が収まり、大丈夫だと確認され吹奏楽部の生徒たちは音楽室に戻りました。
その日の状況は、edulogやツイッターからわかります。地震後、JR中央線が止まってしまい、生徒たちは帰宅するのが困難な状態となってしまいました。会議を経て、本校が取った策はできるだけ自宅の近くまで生徒を送り届ける、ということ。校内にいた生徒を会議室に集めて状況を説明した後、チャーターしたバスと本校のマイクロバスで高尾まで送り届けました。大月方面の生徒はそちらに住んでいる教員の自家用車に乗せて近くまで送り届けました。ただ、停電で信号機もついていない状態で交通渋滞が起きていて、到着するのはかなり時間がかかりました。
連絡係に残った教員(私もその中の1人です)は、つながらない電話を何度もかけ直してくれてやっとつながった保護者の電話への対応をしました。まだ帰らない、という心配の声、無事帰ってきたというお礼の声。その一方で、少ない情報を夜中までツイッターで流し、少しでも状況をわかってもらおうとしました。
当時のツイッターはツイログでご覧になれます。また当日(2011年3月11日)のedulogはこちらです。
学校行事だけでなく、新入生招集日も中止となり、特進チャレンジもなくなりました。新入生と初めて会うのが試験の時以来、入学式が初めてという状態でした。入学式も開催が危ぶまれたほどでした。様々な制約の中で平成23年度が始まりました。
その時に入学した生徒も昨年3月、本校を卒業しました。月日が過ぎるのは早いです。本校も大変な1日でしたが、震災の被災地は原発の問題も絡んでまだまだ大変な状況にあります。忘れてしまうなんてとんでもない。この日を迎えると毎年、本校の大変だった1日のことを思い出し、そこから被災地のことに思いをよせる日とがすくなくともここにはたくさんいます。私たちには何も出来ませんが、思いはひとつに。被災地で犠牲になられたみなさんのご冥福をお祈りしますとともに、現在も被災地その他でがんばっているみなさんに心からお見舞いの言葉を捧げたいと思います。
みなさんはあの時、どこで何をしていましたか。

| オンライン版学校案内2015 日大明誠高校紹介ビデオ2015 教育旅行ガイド2010 (明誠高校の公式サイトが紹介されています) 日大明誠高校エデュログ・バックナンバー |