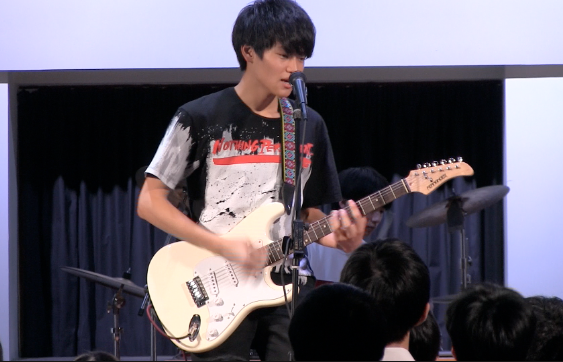1月31日(土)にEPSOM COLLEGE、BURGESS HILL GIRLS SCHOOL両校のバレーボール部が来校し、対抗戦を行いました。
以下、本校男女バレーボール部長の感想です。
* * * *
念願の立教カップ。2学期から市川先生に頼んでいた。やっときた!という気持ちで臨んだが、なんと主力2人が出られないという事態になった。今いるメンバーで勝つしかない。キャプテンとしてそれしかメンバーに言えなかった。
そして1回戦のVS EPSOM。普段とは全く違う感覚。メンバー、環境、歓声が僕たちの平常心を狂わせた。挽回するも敗北。内容、展開、ムード、全てが最悪だった。
なんとか次の試合は勝利。決勝でまたEPSOMと戦うことになった。頼れる高校2年生の2人の欠場、1回戦の悪夢、全てがのしかかってくると思われた。しかし僕らは違った。今いないメンバーの分まで存分にプレーして勝つ、それが僕らの役目だと。試合は1回戦とは見違えるように変わり、皆が自信をもってプレーした。そして勝った。
僕らはチームとして一皮むけた。そう実感した。僕らはチームだ。チームメイトが出られなかったとしても、僕らはつながっている。どこにいようとチームメイト全員で戦う、それがチーム。そう感じることができた立教カップだった。
(高等部2年生 男子バレーボール部長)
* * * *
今回の立教カップには、現地校2校が参加してくれました。試合中や相手をもてなす際、イギリス人だけでなく様々な国の人たちと英語を使ってコミュニケーションを取ることができ、日頃学んでいる英語を使うとても良い機会でした。
女子バレーボール部は男子バレーボール部と比べると人数が少なく、毎日の結果が表れにくいのですが、今回立教カップで行われた全ての試合から、日頃の成果やこれからの目標を見つけられただけでなく、とても多くの事を学ぶ事ができました。
慣れない試合で3位になりましたが、みんなで全力を出せました。
私は高校2年生でもうすぐ引退するのですが、次また開催したときは、優勝して欲しいと思います。開催してくださった先生方、ありがとうございました。