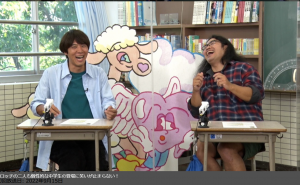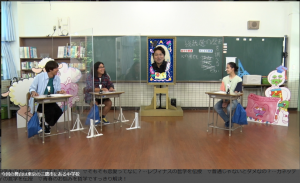総合探究科では、この夏休みに『オリジナルWEBサイト制作講座』を開講しました。集まったのは15人の中学2年生。開講初日、参加しようと思ったきっかけは?と聞くと、「webサイトの仕組みに興味があったから!」「プログラミング、ちょっとやったことがあるので..」「初めてだけど何かおもしろそうだと思ったから〜」などなど、さまざまな反応が返ってきました。自分の得意や興味に気づくこと、これもこの講座の目的の1つです。
総合探究科では、この夏休みに『オリジナルWEBサイト制作講座』を開講しました。集まったのは15人の中学2年生。開講初日、参加しようと思ったきっかけは?と聞くと、「webサイトの仕組みに興味があったから!」「プログラミング、ちょっとやったことがあるので..」「初めてだけど何かおもしろそうだと思ったから〜」などなど、さまざまな反応が返ってきました。自分の得意や興味に気づくこと、これもこの講座の目的の1つです。
3日間で7時間半というタイトなスケジュール。授業は、ライフイズテックレッスンの教材を使い、実際のプログラミング編集ソフトを活用して、オリジナルのWEBサイトを制作するという内容です。(ライフイズテックレッスンHP:https://lifeistech-lesson.jp)
まずは初日、参加した生徒たちはWEBサイトでは欠かせない「HTML」「CSS」の仕組みやプログラミングコード(命令書)について学び、実際にコードを入力していきました。普段からパソコンが身近にある世代。操作の理解や作業がとても速く、2日目にはオリジナルWEBサイトの制作に入ることができました。オリジナルWEBサイトの制作では、1日目に作成したコードを書き換えたり、新たなコードを加えたりしながら、発信したい情報(イメージ)を可視化していきます。ついデザインばかりに気を取られてしまいがちですが、受信者の立場に立って構成を考えることもWEBサイト制作には大事な視点です。
プログラミングの作業に入る前に、テーマを決め、誰に見てほしいのか、見た人にどのような行動変容を起こしたいのか考えた上で、WEBサイトのデザインや構成を考えます。ここまできらたら、あとはプログラミングコードを入力していくだけです。自分のイメージがプログラムによって表現できたとき、感動の声が上がりました。
プログラミングは入力の順番、使用する記号がすべて決まっています。入力に少しでも誤りがあると、本来表示されるべき内容が画面に反映されません。コードは全て英語。アルファベットにミスがあるのか、論理構造に問題があるのか、あらゆる可能性を含めて問題解決に迫る必要があります。なかなか根気のいる作業であるにも関わらず、参加した生徒たちは日に日に真剣な表情になっていきました。最後の発表場面では、発見と冒険に満ちた「探究する」生徒たちの姿があったように思います。
1月に行われるコンクールにエントリーしてみようか?また冬休みに開講してほしいなぁ、そんな会話をして終えたプログラミング講座。動き出した探究心は秋に向かって走り出しています。
(総合探究科担当 新坂彩子)