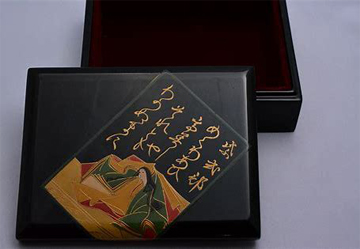
今学期、高校2年生の古文の授業では、「贈る」をテーマに百人一首の中からとっておきの一首を選び、誰かに「贈る」ことからはじまりました。合わせて「うしろめたさの人類学(松村圭一郎)」の冒頭部を読み、「交換」と「贈与」のちがいについても考えました。「贈る」行為には、見返りを求めないことや選ぶ/受け取るまでに物語性があること、また相手を想うからこそ緊張感が伴うなど、身近な経験に基づいた様々な意見が寄せられました。
5・7・5・7・7からなる形式に合わせてメッセージを婉曲的に伝えるという和歌の手法には、現代のテキストメッセージに比べて「贈る」性質が色濃くあらわれているとも考えます。日常のなかにも「言葉を贈る」コミュニケーションを取り入れたり、季節や「音」にちなんだ表現技巧に興味を持ってくれる生徒が少しでも増えてくれると嬉しいです。
今回は、生徒作品を2回に分けてご紹介します。
★ 選んだ和歌:7・天の原 ふりさけ見れば春日なる 三笠の山に出でし月かも
> 大空をふり仰ぐと、月が輝いている。故郷の春日にある三笠山に出ていた、あの月なのだ。
贈る相手:姉
> 立教での生活が再びはじまり、友達と一緒に星を見に行った時に、たまたま大きくて丸い月が輝いているのが見えた。そんな時に、日本にいる姉は元気だろうか、、という気持ちになった。日本への帰国を前にして、故郷の風景や、離れ離れの姉との再会のことが頭に思い浮かんだ。故郷の空と今見える夜空とを比べ思い浮かべた時に、姉も同じ月を見ているような気がしたから、そのことを姉に伝えたいと思った。
★選んだ和歌:11・わたの原 八十島かけて漕ぎ出でぬと 人には告げよあまの釣舟
> 大海原の島々を目指して漕ぎ出しましたとみんなに伝えてください。漁夫の釣舟よ。
贈る相手:両親
> 寮生活によって、半分ひとり立ちした状態であるとともに、あと一年で私は本当に家を出て、自分の力で生きていかなければなりません。その決意と感謝の想いをこめて、この歌を選びました。
★選んだ和歌:12・天つ風 雲の通ひ路吹き閉じよ 乙女の姿しばしとどめむ
> まるで天女のような舞姫と少しでも長く一緒にいたいから、空に吹く風は天女が通る道を閉じてくれないか。
贈る相手:わたしの「推し」
> わたしの「推し」はいつもかわいく、ライブで会ったあとは幸せな気持ちになる。私にとって、まるで天女のような存在です。いつもかわいくて、しあわせくれてありがとう!大好きだよ!
★選んだ和歌:37・白露に 風の吹きしく秋の野は 貫きとめぬ玉ぞ散りける
> 秋の野で、ひかる白露に風がしきりに吹きつける。まるで糸に通していない真珠が散らばっていくようだ。
贈る相手:両親
> 「糸で通していた真珠が散る」というところに、私と両親の関係性を重ね合わせた。両親が私を育ててきた年数を真珠に喩え、「真珠は散らばってしまう」ことは、いつか私が家を出て、ひとりで生きていくことを表していると考えた。真珠は散らばってしまうが、それはこれまでの私たちの関係が無駄になるのではなく、これからの新しい親子関係が築きあげられていく様子であると思う。https://www.rikkyo.co.uk/new/latestnews/ancient-writings-class-report-h2-01/




 高1最後のアウティングは、今までで一番充実していたアウティングだった。この日は、SOHO周辺での昼食、大英博物館、チャイナタウンでの夕食にBack to the futureのミュージカルを見るという盛り沢山な内容だった。アウティング前日に2学期にも一緒に行ったメンバーでグループになり、どこでご飯を食べるかを一緒に考えた。普段食べられない日本食や中華を食べることに決めたその時からワクワクが止まらなかった。何しろ皆で初めてロンドンに行けるのだから。
高1最後のアウティングは、今までで一番充実していたアウティングだった。この日は、SOHO周辺での昼食、大英博物館、チャイナタウンでの夕食にBack to the futureのミュージカルを見るという盛り沢山な内容だった。アウティング前日に2学期にも一緒に行ったメンバーでグループになり、どこでご飯を食べるかを一緒に考えた。普段食べられない日本食や中華を食べることに決めたその時からワクワクが止まらなかった。何しろ皆で初めてロンドンに行けるのだから。







