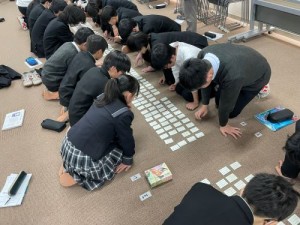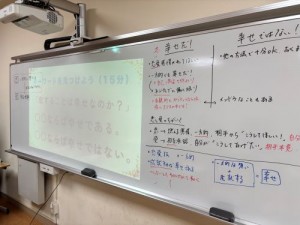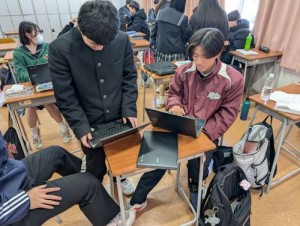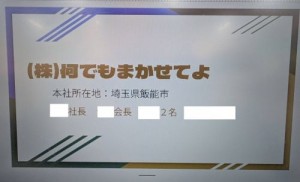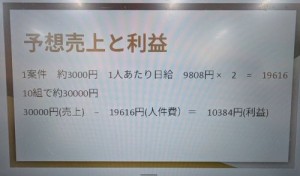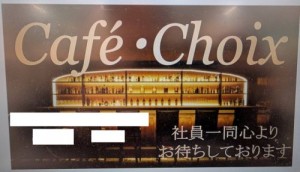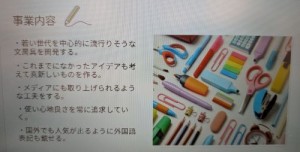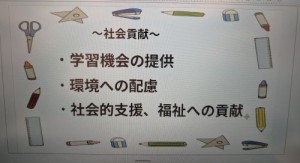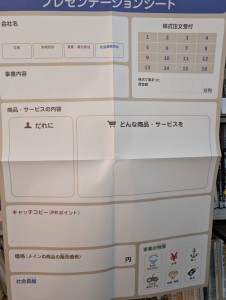1月25日(日)、新人大会初戦(3回戦)が行われ、中央国際高校に19-0で勝利することができました。
相手が9人での試合となり、前半は普段と勝手の違う展開に戸惑いも見られましたが、後半は数的優位を活かし、得点を重ねることができました。最終的には前半6-0、後半13-0と大量得点での勝利となりました。
寒い中、たくさんの応援をいただきありがとうございました。
[3回戦]
1/25(日)12:00 kickoff
vs 中央国際 @東久留米総合
結果:19-0(前半:6-0、後半:13-0) 勝利
【Next Match】
[準々決勝]
2/8(日)9:30 kickoff
vs 拓殖大学第一 @拓殖大学第一
次戦も引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。
[ご来場時のお願い]
・原則、公共交通機関をご利用ください
・お車の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください
・近隣商業施設への駐停車はご遠慮ください