読売新聞オンライン(中学受験サポート)にて、本校「木工の授業」の取材記事が掲載されました。
是非、ご一読ください。
(中学校副校長 堀内)
NHKEテレの哲学バラエティー番組『ロッチと子羊』の明星学園中学校編第2弾が、以下の日程で放映されます。
9月29日(木)
NHKEテレ
午後8時~8時半
https://www.nhk.jp/p/ts/N9GR16WRR6/episode/te/8VJPQN6N1Y/
今回は9年生二人のお悩み。「好きなことはできるのに、苦手なことだと集中できない」「どう人に思われるかが気になって、友達と気軽に話せない」。どちらも多くの中学生が多かれ少なかれ感じている悩みではないでしょうか。
15日(木)に放映された第1弾では8年生の二人が登場し、大好評でした。「恋愛って何?」「周りの普通が気になって、自分を出すことを抑えてしまう」。おとな自身が立ち止まって考えさせられます。是非、ご覧ください。
(中学校副校長 堀内)
本校では、毎年秋に「公開研究会」を実施しています。この研究会は今年度取り組んできた教育内容について、教育方法について、広く他校の先生方や研究者の皆さま、教員を目指す学生の方々に公開し、ご意見を伺う場です。私たちにとっては大きな刺激となり、共に学ばせていただく貴重な機会となっています。
今年度もコロナ禍の中の公開研究会、オンラインという形となりますが、全体会には哲学者の西谷修氏をお迎えし(YouTube動画で配信)、5教科での分科会を持ちます。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
(副校長 堀内)。
今年度最後となる第4回『体験入学』の申し込み受付が始まりました。
次の4つのコースよりお選びいただけます。
10月30日(日)8:45集合 9:00~11:30
Aコース 国語&理科
Bコース 数学&社会
Cコース 社会&英語
Dコース 理科&数学
中学校の教室を会場に、明星学園の授業の特色を感じ取っていただけるのではないかと思います。
毎年、体験授業を受けて、明星を受験することに決めたという受験生がたくさんおります。
授業内容等、詳細はこちらのページをご覧ください。
また、第4回『学校説明会』も同時に募集しております。
10月15日(土)
14:00~(来校型)/16:00~(来校型)/オンライン配信
詳細、お申し込みはこちらのページをご覧ください。
(中学校副校長 堀内)
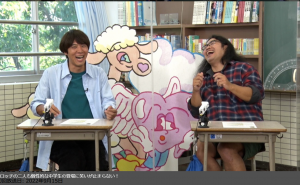 NHKEテレの哲学番組『ロッチと子羊』は昨年の6月、明星学園が協力する形で第1回が放映されました。明星生3人が自分のお悩みをロッチに相談。中岡さんとコカドさんがその悩みを掘り下げてくれます。そこに登場するのが哲学者の小川仁志教授(山口大学)。同じテーマについて深く考えていた哲学者とその言葉を解説、紹介してくれます。中学生の悩みというのは、本質的で、深い哲学的なテーマなのです。
NHKEテレの哲学番組『ロッチと子羊』は昨年の6月、明星学園が協力する形で第1回が放映されました。明星生3人が自分のお悩みをロッチに相談。中岡さんとコカドさんがその悩みを掘り下げてくれます。そこに登場するのが哲学者の小川仁志教授(山口大学)。同じテーマについて深く考えていた哲学者とその言葉を解説、紹介してくれます。中学生の悩みというのは、本質的で、深い哲学的なテーマなのです。
その後、さまざまな社会人のお悩みを対象にしながら番組は不定期に放映されてきましたが、この4月から毎週木曜午後8時からのレギュラー番組となり、再び明星学園中学校に戻ってきてくれました。
今回は明星生4名、30分で2名が登場するので、番組2本分です。
前回と同様、中学校校舎4階の教室で収録が行われました。
第1弾の放映は次のとおりです。
NHKEテレ 9月15日(木) 午後8時~8時半
8年(中2)の2名が登場します。
NHKの番組告知ホームページはこちらから。
これは偶然なのですが、番組の独特なタッチのイラストを担当しているAZY(あじー)さんも明星学園の卒業生でした。びっくりでした。
なお、第2弾(9年生の2名が登場します)も近日中に放映予定です。

 昨日(9月6日)、中学校では2校時~4校時を特別時間割とし、「JOES Davos Next 2022 ~ GLOBAL STUDENT SUMMIT ~」に参加しました。
昨日(9月6日)、中学校では2校時~4校時を特別時間割とし、「JOES Davos Next 2022 ~ GLOBAL STUDENT SUMMIT ~」に参加しました。
各教室ごとにウェビナーでつなぎ、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授(京都大学iPS細胞研究所名誉所長・教授)のオンラインライブ配信を聞きました。
海外の日本人学校やインターナショナルスクールを含む9500人以上の中学生が参加したとのことです。医学を志したきっかけから始まり、挫折を経験しながらも研究者の道を歩んでいったこと、iPS細胞について、講演を聞いてくれている中学生へ向けてのメッセージ、とてもソフトな語り口でお話ししてくれました。
山中教授が今でも忘れられない恩師からの言葉。研究者として成功するための秘訣。それは「VW」。「Vision」(魅力的なビジョンを考えること)と「Work Hard」(懸命に努力すること)。何事にも当てはまるような気がします。
第2部は質疑応答のコーナー。海外から視聴している中学生が何人も登場、今この時間にこれだけの中学生が繋がっているのだということを実感しました。「まだ夢を持っていなくても心配することはない。目の前にあることにしっかり向き合って行動していれば、自然と見つかるものだ。私だって30になってから大学院に入り直して研究者になろうとした。でも小さいころから好きなことはあった」。生徒たちはどんなことを感じたでしょうか。
第4回学校説明会(10月15日実施)の申し込み受付が始まりました。
当初は来校型の参加は「14時から」の1回を予定しておりましたが、密を避けるため、「14時から」「16時から」の2回の設定に変更いたしました。
申込フォームが分かりづらいかと思いますが、ご都合に合わせてお選びください。
もちろん、オンライン参加も可能です。
内容は校長の挨拶、副校長の学校概要に続き、今回の授業説明は本校独自の「木工」の授業について。
また、在校生が本校の目玉の取り組みともいえる「卒業研究」について語ります。
今年度最後の「学校説明会」となります。
当日お会いできるのを楽しみにしています。
詳細はこちらから。
(副校長 堀内)
8月29日に明治神宮至誠館第二弓道場で行われた第74回「 東京都中学校弓道大会」で女子団体、男子団体がそれぞれ決勝進出を決めました。女子団体は決勝8位の活躍、男子団体は見事優勝しました!
また、個人では野中桃子さん、岩田匠生くん、唐梨子俊くん、儀武湧來くんの4人が決勝に進出し、岩田匠生くんが個人3位の活躍を見せてくれました。
特に男子団体の決勝では、結果が出る前からやることはやり切ったぞという満足感が出ていたのが印象的でした。
<大会結果>
○女子団体 【8位】(24射5中)
野中 桃子/松本 紗良/松永 樹里
○男子団体 【優勝】(24射12中)
唐梨子 俊 8射4中
清水 錬 8射3中
岩田 匠生 8射5中
○女子個人
野中 桃子 8射3中 【4位タイ】
○男子個人
岩田 匠生 8射5中 【3位】
唐梨子 俊 8射4中 【4位タイ】
儀武 湧來 8射3中 【7位タイ】
*中学校弓道部の紹介はこちらから。写真がふんだんのコンテンツです。
*他のオリジナル取材記事(12のテーマ)はこちらから。
(中学校弓道部 木暮)

 総合探究科では、この夏休みに『オリジナルWEBサイト制作講座』を開講しました。集まったのは15人の中学2年生。開講初日、参加しようと思ったきっかけは?と聞くと、「webサイトの仕組みに興味があったから!」「プログラミング、ちょっとやったことがあるので..」「初めてだけど何かおもしろそうだと思ったから〜」などなど、さまざまな反応が返ってきました。自分の得意や興味に気づくこと、これもこの講座の目的の1つです。
総合探究科では、この夏休みに『オリジナルWEBサイト制作講座』を開講しました。集まったのは15人の中学2年生。開講初日、参加しようと思ったきっかけは?と聞くと、「webサイトの仕組みに興味があったから!」「プログラミング、ちょっとやったことがあるので..」「初めてだけど何かおもしろそうだと思ったから〜」などなど、さまざまな反応が返ってきました。自分の得意や興味に気づくこと、これもこの講座の目的の1つです。
3日間で7時間半というタイトなスケジュール。授業は、ライフイズテックレッスンの教材を使い、実際のプログラミング編集ソフトを活用して、オリジナルのWEBサイトを制作するという内容です。(ライフイズテックレッスンHP:https://lifeistech-lesson.jp)
まずは初日、参加した生徒たちはWEBサイトでは欠かせない「HTML」「CSS」の仕組みやプログラミングコード(命令書)について学び、実際にコードを入力していきました。普段からパソコンが身近にある世代。操作の理解や作業がとても速く、2日目にはオリジナルWEBサイトの制作に入ることができました。オリジナルWEBサイトの制作では、1日目に作成したコードを書き換えたり、新たなコードを加えたりしながら、発信したい情報(イメージ)を可視化していきます。ついデザインばかりに気を取られてしまいがちですが、受信者の立場に立って構成を考えることもWEBサイト制作には大事な視点です。
プログラミングの作業に入る前に、テーマを決め、誰に見てほしいのか、見た人にどのような行動変容を起こしたいのか考えた上で、WEBサイトのデザインや構成を考えます。ここまできらたら、あとはプログラミングコードを入力していくだけです。自分のイメージがプログラムによって表現できたとき、感動の声が上がりました。
プログラミングは入力の順番、使用する記号がすべて決まっています。入力に少しでも誤りがあると、本来表示されるべき内容が画面に反映されません。コードは全て英語。アルファベットにミスがあるのか、論理構造に問題があるのか、あらゆる可能性を含めて問題解決に迫る必要があります。なかなか根気のいる作業であるにも関わらず、参加した生徒たちは日に日に真剣な表情になっていきました。最後の発表場面では、発見と冒険に満ちた「探究する」生徒たちの姿があったように思います。
1月に行われるコンクールにエントリーしてみようか?また冬休みに開講してほしいなぁ、そんな会話をして終えたプログラミング講座。動き出した探究心は秋に向かって走り出しています。
(総合探究科担当 新坂彩子)
 『高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会』硬筆の部で9年生(中3)の松崎ほの里さんが日本武道館奨励賞を受賞しました。
『高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会』硬筆の部で9年生(中3)の松崎ほの里さんが日本武道館奨励賞を受賞しました。
また、国語の授業の一環で取り組んだ明星学園中学校には2年連続で「優良団体賞」が贈られました。
松崎さんは、日本武道館で行われた授賞式(8月28日)に出席しました。
日本武道館は、昭和39年(1964)の開館以来、「武道を通して青少年の健全育成」という設立目的に沿って、文武両道の立場から、日本の伝統文化のひとつである書写・書道の普及奨励を図るため、昭和60年(1985)から「高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会」を開催しています。「高円宮杯」を最高賞にいただく本展覧会は、名実ともに権威ある全国的な書写書道大展覧会として、今年で第38回を迎えます。
(国語科 山口)
ページ
TOP