9月5日(月)19:30~20:00にNHKのEテレで放送される「沼にハマってきいてみた」の「ぬまろく」のコーナーに高校ファッション部が出演予定です。
番組URLはこちら
「スパイス沼 幻のスパイスを入手せよ!」
また、今後も中高生のNHKの番組への登場が続きます。
直前になるまで情報解禁とはなりませんが、この「エデュログ」を通してお知らせしていきます。
よろしくお願いします。
(中学校副校長 堀内)
9月5日(月)19:30~20:00にNHKのEテレで放送される「沼にハマってきいてみた」の「ぬまろく」のコーナーに高校ファッション部が出演予定です。
番組URLはこちら
「スパイス沼 幻のスパイスを入手せよ!」
また、今後も中高生のNHKの番組への登場が続きます。
直前になるまで情報解禁とはなりませんが、この「エデュログ」を通してお知らせしていきます。
よろしくお願いします。
(中学校副校長 堀内)
9月17日(土)に実施予定の第3回「体験入学」の申し込み受付が、明日8月29日(月)9時より始まります。
今回は実技系3コース、定員が限られているため受付開始すぐに定員に達してしまう教科も出てくるかもしれません。
早めのお申し込みをお願いします。
Aコース(木工)・・・定員15名
Bコース(工芸)・・・定員18名
Cコース(体育)・・・定員15名
☆6年生限定、また第2回体験入学に参加された方はお申し込みできません。何卒ご了解ください。
詳細は、こちらのページよりお願いします。
(副校長 堀内)
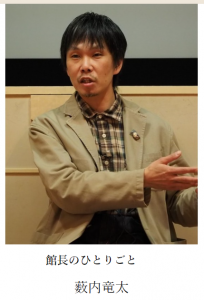 6月から始まった明星学園創立100周年記念「リレーエッセイ」、尾木直樹氏・鈴木健次郎氏に続く第3弾は 薮内正幸美術館館長 薮内竜太氏(卒業生 55回生)。
6月から始まった明星学園創立100周年記念「リレーエッセイ」、尾木直樹氏・鈴木健次郎氏に続く第3弾は 薮内正幸美術館館長 薮内竜太氏(卒業生 55回生)。
タイトルは、『館長のひとりごと』。
こちらからご一読ください。
薮内氏は1969年東京生まれ。父は動物画家である薮内正幸(1940~2000)、母は福音館書店の編集者(児童書担当)を経て、フリーライターでありタイ料理研究家でもあった戸田杏子(本名:薮内幸枝 1941~2006)。大学卒業後はJRの外郭団体に勤務するものの2000年の正幸死去に伴い退社、以後遺された1万点以上もの原画の管理を専属で行う。
明星学園で小中高12年間を過ごした母親の前向きな生き方、その影響を受け、館長になってしまったいきさつとその思いがユーモアたっぷりに語られています。
<父 薮内正幸氏>
1940年大阪生まれ。幼少時代より生き物に興味を抱き、身近な生物の飼育に明け暮れる。小学生の頃より始まった動物園通い、動物学者との文通を通じ動物の知識を得て、あわせて独学で動物画を描き始める。
高校卒業と同時に哺乳類図鑑を出版予定だった福音館書店に入社、国立科学博物館に日参して動物の骨格標本の模写を続ける。
1965年に「くちばし」で絵本デビュー、翌年の「どうぶつのおやこ」、1969年のかがくのとも創刊号「しっぽのはたらき」(全て福音館書店)など多数の絵本、「冒険者たち ガンバと十五ひきの仲間」(岩波書店)などの物語挿絵、広辞苑、世界大百科事典など図鑑挿絵、記念切手(自然保護シリーズ「アホウドリ」1975年)や広告などへ動物画を提供。また1973年に始まったサントリー愛鳥キャンペーンでは朝日広告賞第2部グランプリ、「コウモリ」(福音館書店1983年)で第30回サンケイ児童出版文化賞、「日本の恐竜」(福音館書店1989年)で第9回吉村証子記念日本科学読物賞を受賞。
2000年6月、逝去。2004年に山梨県北杜市白州町(当時は北巨摩郡白州町)に薮内正幸美術館が開館。
*今後も月1回のペースで、さまざまな分野で活躍する明星学園ゆかりの方々でエッセイをつないでいきます。ご期待ください。
(中学副校長 堀内)
9月3日(土)の学校説明会、当初来校型は14時からの部一回としていましたが、新たに16時からの部を作り、現在申し込み受付中です。
おかげさまで14時からの部は定員に達しています(8/25時点)が、16時からの部には空きがございます。
是非、学園に足を運んでいただき、学園の空気を感じていただければと思います。
今回の説明会の内容は以下のとおりです。
①校長挨拶
②学校概要
③明星の授業(英語の授業を例に)
④生徒自治会について
⑤在校生の話
⑥2023年度入試について
詳細・お申し込みは、こちらのページよりお願いします。
(副校長 堀内)
今年度第3回「体験入学」(9月17日実施)の申し込み受付が、8月29日(月)9時より始まります。
6年生限定、また、できるだけ多くの方にご参加いただけるよう、第2回の体験入学に参加いただいた方は申込することができません。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、今回は実技教科で人数が限られているため、受付開始すぐに定員に達してしまう教科も出てくるかもしれません。
Aコース(木工) 定員15名
Bコース(工芸) 定員18名
Cコース(体育) 定員15名
ご希望の教科がある場合は、是非早めのお申し込みをお願いいたします。
詳細は、こちらのページよりお願いします。
(中学校副校長 堀内)

 リンデンホールスクール(福岡)中高生有志の皆さん主催の「ウクライナ平和サミット@東京」に9年生(中3)8名と高校生4名が参加しました。
リンデンホールスクール(福岡)中高生有志の皆さん主催の「ウクライナ平和サミット@東京」に9年生(中3)8名と高校生4名が参加しました。
リンデンホールスクール中高生有志の皆さんは、現在、福岡にある大学に避難・留学してきている65名のウクライナ人留学生と出会いました。
そこで留学生たちから、「支援物資を集めるよりも、今の現状を日本の人たちに知ってほしい」という話を聞き、「ニュースで流れる戦争とは違う、ひとりひとりの『戦争』を同世代の日本人中高生に知ってもらい、『戦争』とは何なのか、『平和』の意味は何なのかを自分の中で考えるきっかけを作りたい。そして、ウクライナと日本の若者同士が繋がり語り合うことで、一緒に、どのような世界を築きたいかを議論できる場所にしたい」とクラウドファンディングやスポンサーになってくれる企業を探し、資金を集め、全国6か所で「平和サミット」を企画したそうです。
当日は、明星学園の12年生(高3)と9年生(中3)が1人ずつパネリストとして参加。ウクライナの文化や歴史の紹介から始まり、3人のウクライナ人留学生が直面した「戦争」の話を聞き、ウクライナ人と日本の中高生とのディスカッションを重ねました。
詳細はこちらからご覧ください。ウクライナ留学生とのやり取りや感想を載せています。
また、この時の様子などが、NHKの「ニュースウォッチ9」(8/15)「日本の中高生たちとウクライナの避難者が「平和」について議論」で報道されました。本校9年生(中3)のパネラーとウクライナの学生のやりとりも取り上げられていますので、ぜひ合わせてご覧ください。
(中学校副校長 堀内)
 私立中学情報サイト『ココロコミュEAST』による明星学園中学校のコンテンツ(取材記事)まとめページです。
私立中学情報サイト『ココロコミュEAST』による明星学園中学校のコンテンツ(取材記事)まとめページです。
学校パンフレットとはまた違う、テーマを絞った深い学校紹介になっています。写真も豊富で、関心のあるところからご覧いただければと思います。
学園の教育理念・明星教育を体現する授業・芸術教育・クラブ活動・卒業生の声・・・・・・
ココロコミュ学校情報ページはこちらから!!
(中学副校長 堀内)
 8月9,10日、神奈川県平塚市レモンガススタジアムにて第50回関東陸上競技選手権大会が行われました。7月に行われた2つの都大会で、成績の上位3人の選手がこの関東大会に東京都代表選手として出場できます。明星学園からは共通男子400mに小澤選手が出場しました。400mは初日に予選が3組で行われ、各組2着以内の選手と3着以下の全ての選手の中でタイム上位2選手が、2日目の決勝へと駒を進めます。大会10日前に左太腿を痛めた状態での出走でしたが、意地を見せて見事6位入賞を果たしました。
8月9,10日、神奈川県平塚市レモンガススタジアムにて第50回関東陸上競技選手権大会が行われました。7月に行われた2つの都大会で、成績の上位3人の選手がこの関東大会に東京都代表選手として出場できます。明星学園からは共通男子400mに小澤選手が出場しました。400mは初日に予選が3組で行われ、各組2着以内の選手と3着以下の全ての選手の中でタイム上位2選手が、2日目の決勝へと駒を進めます。大会10日前に左太腿を痛めた状態での出走でしたが、意地を見せて見事6位入賞を果たしました。
詳細はこちらからお読みいただけます。
(副校長 堀内)
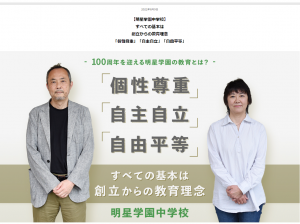
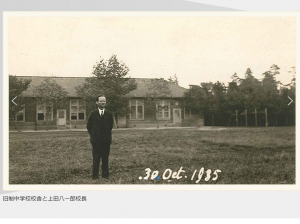 私立中高情報サイト「ココロコミュEAST」に明星学園の記事が掲載されました!
私立中高情報サイト「ココロコミュEAST」に明星学園の記事が掲載されました!
タイトルは、『明星学園中学校—すべての基本は創立からの教育理念~「個性尊重」「自主自立」「自由平等」』
創立当時の写真も登場します。また、先人たちの残した言葉が対談記事の間に挟み込まれる構成になっていますが、それらが今まさに必要な言葉であると感じます。
明星学園の教育理念がどのような形で今に受け継がれ、21世紀の現在に生かされているかということについて語りました。是非、こちらからご一読ください。
(中学校副校長 堀内)
 8/1(月)、9年生(中3)2名と12年生(高3)1名で、東京外国語大学の吉冨朝子先生の研究室を訪問してきました。
8/1(月)、9年生(中3)2名と12年生(高3)1名で、東京外国語大学の吉冨朝子先生の研究室を訪問してきました。
吉冨先生は、英語を中心とした第二言語習得研究を専門分野として研究されています。今回は、「バイリンガルの頭の中はどうなってるのか」「外国語の早期教育について」という卒業研究に取り組んでいる9年生と、3年前に同じく日本の英語教育に関する卒研に取り組み、そこから発展させ応用言語学に関心を持つようになった12年生が研究する中で出てきた疑問について、お話を伺ってきました。
3人が事前に出していた疑問に答えていただく形で、吉冨先生からたくさんのお話を聞くことができました。個人的には、言語は、「その人が言いたいことを言うためのもの」であり、目的を持って使うことが大事という話、また、今や世界中の様々な国で生活している人達が使う言語になっているので、どの英語の発音が「正しい」というのはない。どれだけ相手に通じるかという明瞭度が大切という話が印象に残りました。
吉冨先生がどうしてこの研究をされるようになったのかご自身の中高生時代のお話も伺うことができ、とても楽しい時間となりました。
また、卒研で取り組んだことをずっと考え続け、自分でさらに興味を深めている12年生の存在が頼もしく、9年生の2人も大いに刺激を受けたことでしょう。
この夏、9年生は、様々な「してみる」ことに挑戦中です。9月には、「してみた」ことなどを報告する中間報告会が予定されています。それぞれがどんなことを「してみた」のかを聞くことができるのを楽しみにしています。
(9年社会科担当 小畑)
ページ
TOP