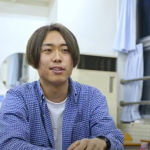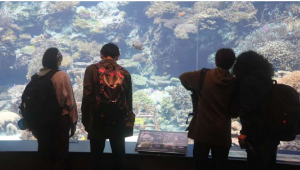
 修学旅行も4日目、今日は伊平屋島を離れ、本島に戻ります。しかし、ここでアクシデントが…。ニュースでも報道されていた「軽石」が運天港に押し寄せた影響で、伊平屋からの9時発の1便が欠航になってしまいました。
修学旅行も4日目、今日は伊平屋島を離れ、本島に戻ります。しかし、ここでアクシデントが…。ニュースでも報道されていた「軽石」が運天港に押し寄せた影響で、伊平屋からの9時発の1便が欠航になってしまいました。
しかし、観光協会の方々、日本旅行の方々のご尽力により、10時半発の本部行きが臨時で出航することが決まりました。そのため、子どもたちは10時に前泊港に向かい、そこで伊平屋の方と最後の挨拶をしました。
笑顔でお別れしている班もあれば、お互い涙を流して別れている班もありました。
フェリーが伊平屋から出港した後、一人の生徒がずっと海を眺めていました。
何かあったのかなと思い尋ねてみると、
「伊平屋に戻りたい。東京に帰りたくない。もっといろんなことをしてみたかった。必ずお金を貯めて、また伊平屋に行きます。」
と言っていました。
昨日の報告にもありましたが、子どもたちは本当に良い表情で過ごしていました。この子もその一人です。
午後からは美ら海水族館に向かい、そして沖縄での最後の夜を南部地域で過ごしました。夕食も広々とした会場で、対面にならないよう配慮していただき、楽しく食事をすることができました。明日は平和祈念公園の見学、国際通りを散策して東京に戻ります。