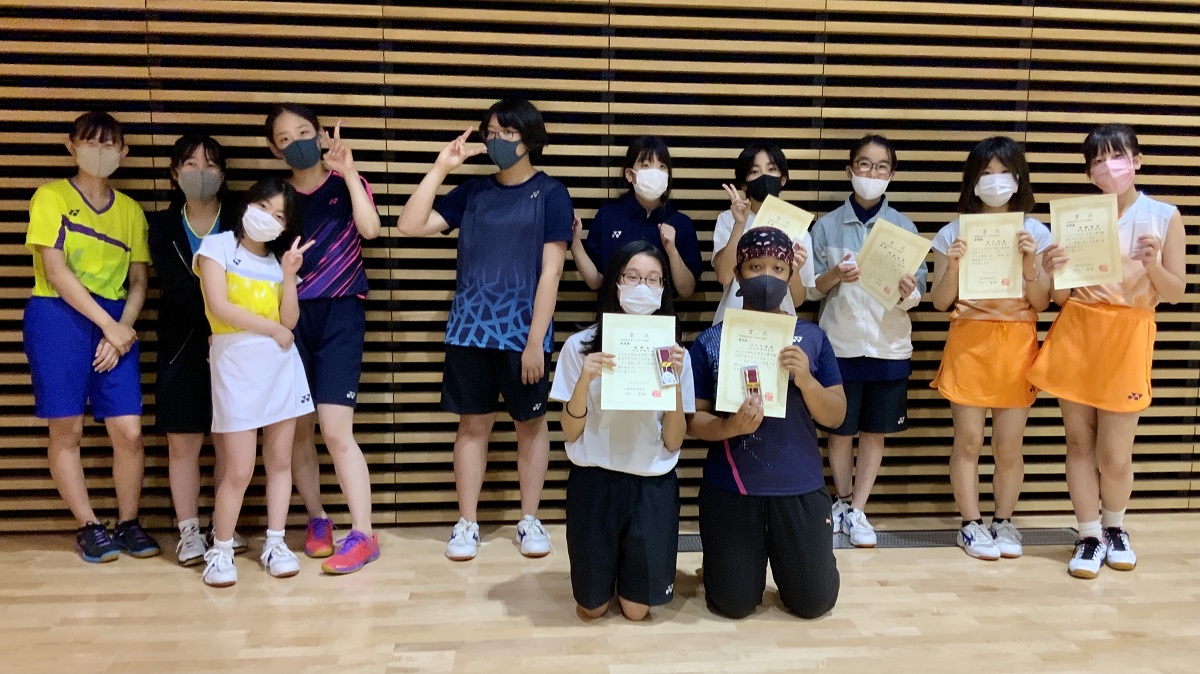一昨日お届けした数学の授業紹介。その中で明星学園中学校では、中1の1学期に「ピタゴラスの定理」を学ぶとお伝えしました。けして先取り学習ではありません。ではなぜ教科書の中3で扱う教材を中学校に入学して間もない1年生を相手に行うのか? ちょうどその単元を参観したときのレポートをお届けします。
一昨日お届けした数学の授業紹介。その中で明星学園中学校では、中1の1学期に「ピタゴラスの定理」を学ぶとお伝えしました。けして先取り学習ではありません。ではなぜ教科書の中3で扱う教材を中学校に入学して間もない1年生を相手に行うのか? ちょうどその単元を参観したときのレポートをお届けします。
◇数学の授業―『中1で学ぶピタゴラスの定理』―「?」から「!」へ <中1‐1学期の実践>
数週間前のことです。受験希望者で学校見学に訪れた方を案内していました。中学校校舎をまわりながら廊下から教室の中の中学生の様子を見てもらっています。2階の廊下に出てみると扉の開いている教室があります。せっかくなので教室の中に入ってみました。数学の授業です。
「『cm』は、何を表す単位ですか?」 ― 「長さ!」
「『c㎡』は、何を表す単位ですか?」 ― 「面積!」
「では、4c㎡の面積の正方形を作図できるね? 9c㎡の正方形はどうかな?」
先生が作図するための用紙を配ると、早速生徒は作業に取り掛かります。その様子を見ながら私たちは教室を後にしました。
次の休み時間のことです。授業者のN先生から声をかけられました。「もう少し見ていてくれたらよかったのに!」 どうも私たちが見たものは授業の導入で、小学生でもできる問題だというのです。実は、この授業での本当の課題は、「13c㎡の正方形を作図しなさい」というものだったようです。格段に難しくなります。2乗して13になるのは…と、計算を始めてみました。3と4の間。3.6と3.7の間。実は生徒もそういう計算を始めたそうです。中にはもっと先まで計算する生徒もいるというのです。そんな生徒に授業者は、「でも、そんな細かい数字を作図できる定規はないよね!」と言います。私も頭を抱えました。
先生は生徒たちに次のようなヒントを与えたそうです。「4・9・13という数字で、何か気づくことはないかな?」私には見当がつきません。ただ、中学1年の教室では必ず誰かが気づくと言います。「これを使えばいいのか!」教室の中でだれが最初に気づくのか。たぶんその発言で多くの生徒が「?」から「!」に変わっていくのでしょう。
そこで私は、N先生にそれまでの授業のノート記録を見せてくれるように頼みました。そして「なるほど!」と思うわけです。実はこの授業の数時間前に、以下のような授業があったのです。ここではその一部を紹介したいと思います。
課題1
同じ大きさの2枚の正方形を切って、すき間が空かないように並べ替えて、一つの正方形を作りたい。さて、どう切ってどう並べかえればよいでしょうか。
生徒は配られた紙に補助線を入れていきます。特に難しい問題ではありません。でも、ノートを見ると生徒から出てきた考えは5種類もありました。「簡単な問題だ!」と私も補助線を入れ、それで済まそうとしていたのですが、5種類の考えを眺めながら「?」、頭が動き始めるのを感じます。生徒から出てきた考えは次の通り。発表者はなぜそれが正方形になるのかを説明できなければなりません。
<生徒の考え>
続きはこちらをどうぞ。
(中学校副校長 堀内)

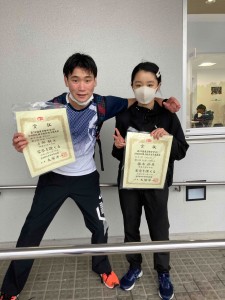



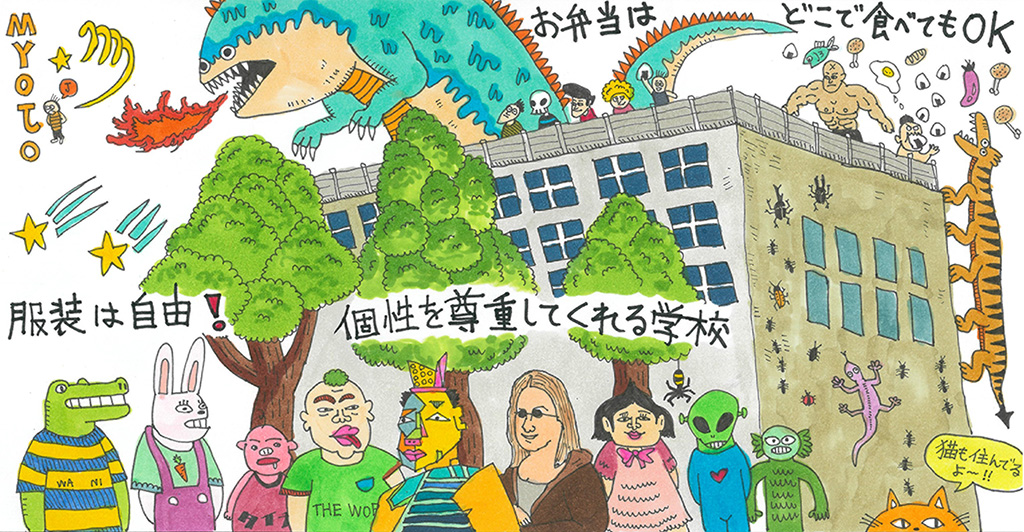
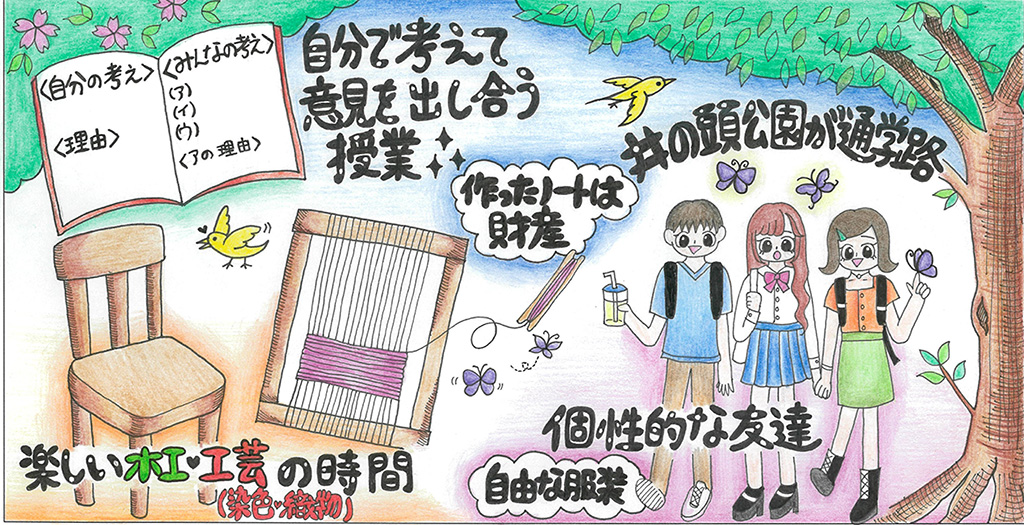






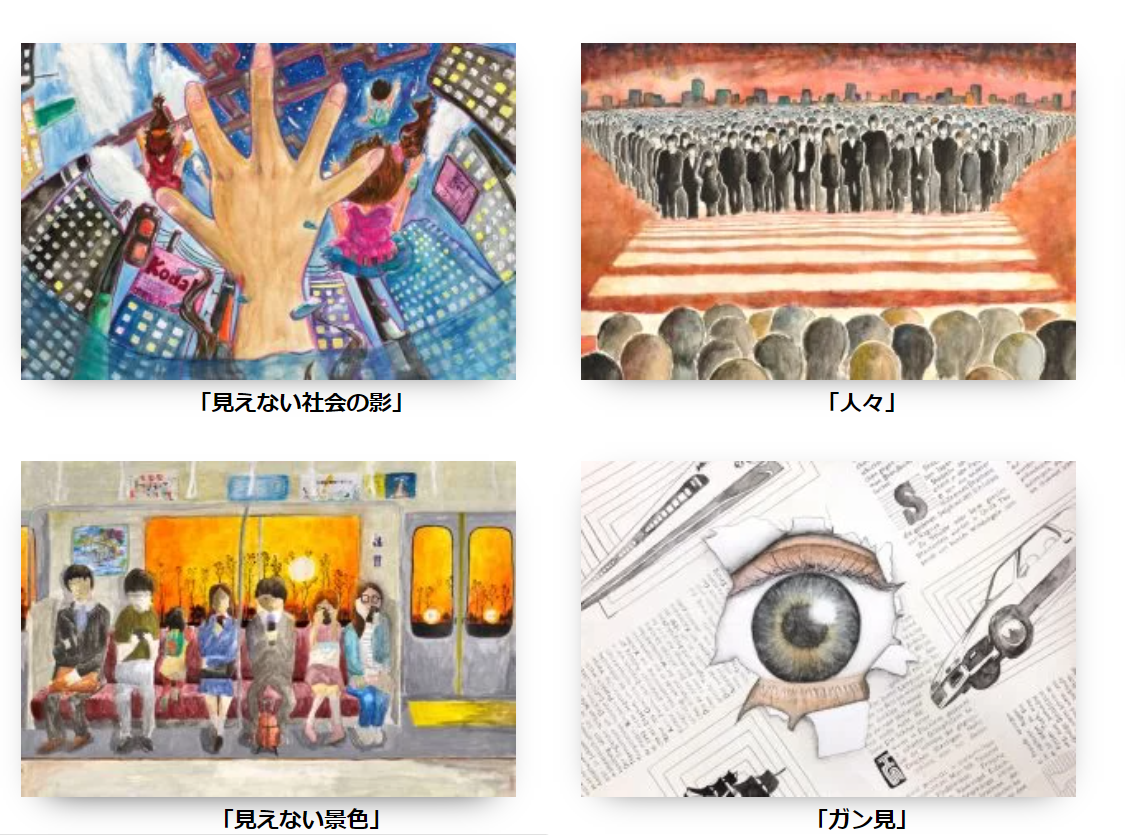
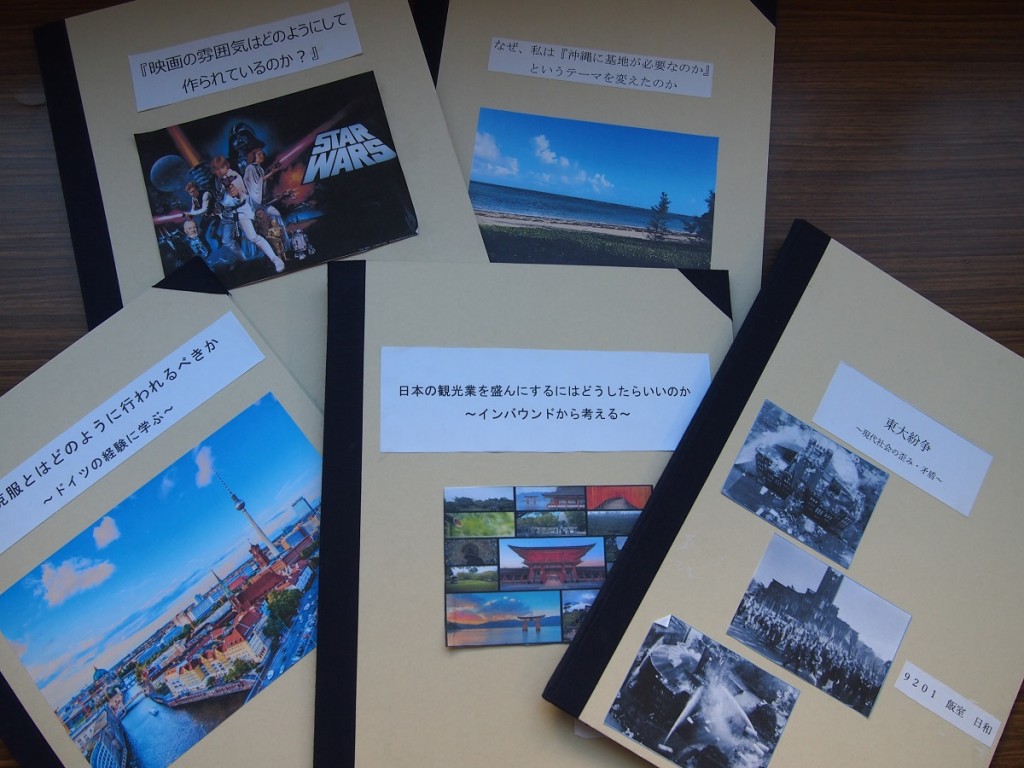

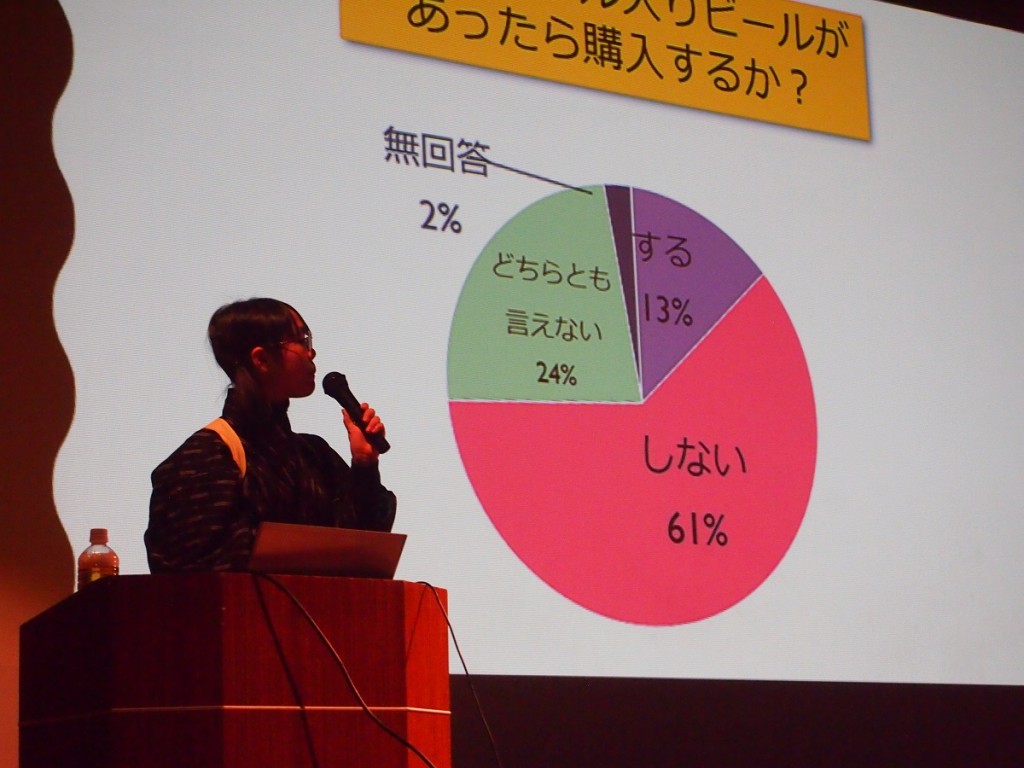
 一昨日お届けした数学の授業紹介。その中で明星学園中学校では、中1の1学期に「ピタゴラスの定理」を学ぶとお伝えしました。けして先取り学習ではありません。ではなぜ教科書の中3で扱う教材を中学校に入学して間もない1年生を相手に行うのか? ちょうどその単元を参観したときのレポートをお届けします。
一昨日お届けした数学の授業紹介。その中で明星学園中学校では、中1の1学期に「ピタゴラスの定理」を学ぶとお伝えしました。けして先取り学習ではありません。ではなぜ教科書の中3で扱う教材を中学校に入学して間もない1年生を相手に行うのか? ちょうどその単元を参観したときのレポートをお届けします。