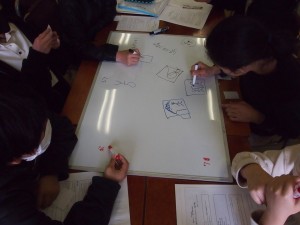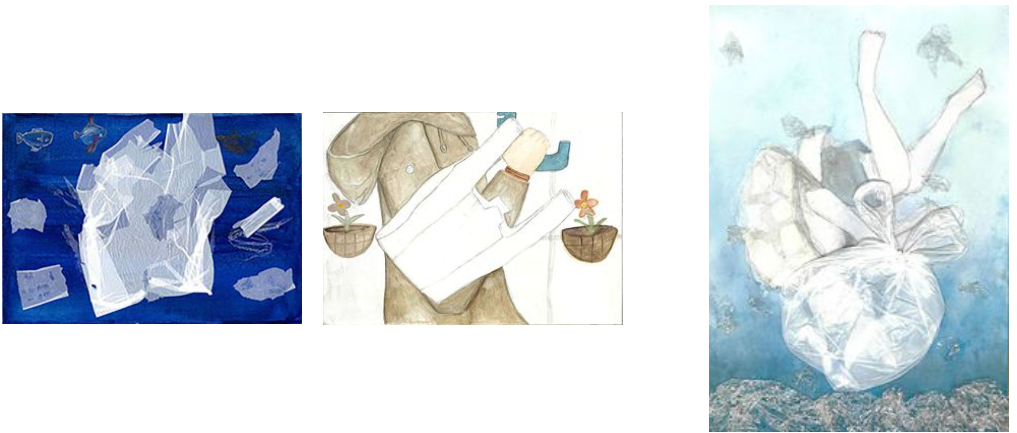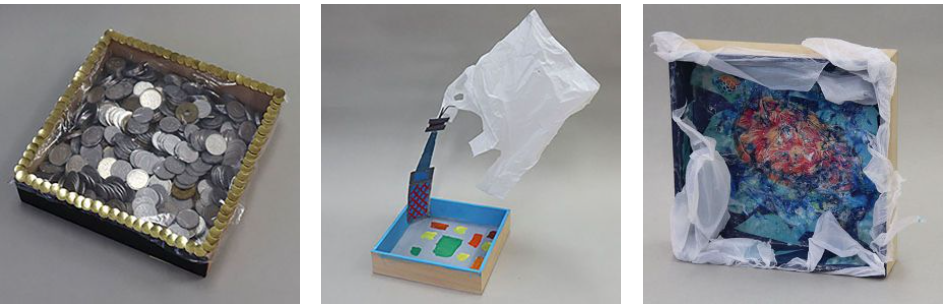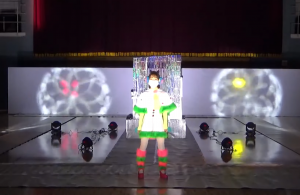3月15日(火)、中学校卒業式が無事終わりました。まん延防止等重点措置期間のため、在校生の参加は叶わず、例年熱い歌声が響き渡る合唱も自粛する形となりましたが、クラスの卒業動画・先生方からのプレゼント動画・花束贈呈など、大変心温まる卒業式となりました。
そのような中でも卒業生代表の4人の言葉には、心揺さぶられました。
それは決して平たんではなかった中学校の3年間、卒業する今だからこそ振り返り、感じられること。目の前にはいないけれど、後輩たちに伝えたいこと。
そんな4人の言葉をここで紹介させていただきます。
◇卒業生代表:カーター和(中3)
初めて体育館の入り口に立ち、中を眺めた時のことをよく覚えています。等間隔に並べられたパイプ椅子と、そこに座った見知らぬ人たちを見て、鼓動がさらに速まるのを感じました。となりの人との、たった2メートルの距離が恐ろしく広く感じられた転校初日からもう2年。あれから2年もたったことが信じられません。
あれが、昨日のようでもあり、一生涯をこの場所で送ったかのようにも感じます。でも本当は、そのどちらも間違いで、正しくは2年なのです。濃い時間でした。
明星は多様性のある学校です。多くの人が共感してくれるのではないでしょうか。ほかでは出会えないような人たちが集まった学校だと思います。決して完璧な人間ばかりだとは言えないけれど、まさしくその、個性的な人の集まりである点こそが私にとってのこの学校の最大の魅力でした。
私は多様性というものは寛容性をもつことを教えてくれると思っています。多様な人々と生活をしていると、必然的に、意見が合わないことが出てきますが、そういうぶつかり合いの経験こそが人として寛容性を持つことに大きく関係しているのではないかと思います。自分とは違う他者を受け入れること。自分とは違う意見を受け入れること。自分よりも弱い、能力のないものを排除するのではなく、認めるということ。自分と異なるものを受け入れる心のゆとりこそが多様性の作り出す最大の宝ではないかと私は感じます。こうした寛容性、心のおおらかさは多様性のある暮らしから学ぶことができると思っています。
寛容性を持つということは、つまり弱者に対して優しさを持つことに深く関係しています。そのような心構えを持っていれば、弱いものを排除しようという思考には至りません。社会に貢献していない人は生きる価値がないなどという思考には至りません。弱者に対する態度というものは人の芯をあらわにすると思います。
例えば今まさに国同士の力関係が語られているウクライナ問題に関しても、弱者に対する見方というのは非常に大きな論点となります。
私の好きな作家の、村上春樹さんがイスラエルの文学賞の受賞スピーチで話した言葉をここで紹介したいと思います。
「もしここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立ちます。」
このスピーチのことに関して言えば、村上春樹さんは、ガザ地域に攻撃を続けるイスラエル軍を暗に批判していたわけですが、つまりは自分は弱者の側に立つということを言っているのです。
誰にも考えを押し付けるつもりはありません。ただ私も同じように、常に弱者の味方でありたいと思います。弱者と共に戦える人でありたいと思います。
弱きものを受け入れられる人というものは強く、優しい人だと思いますし、同様に弱きものを守れる社会は強く、優しい社会だと、私は思います。
多様性のある空間は寛容性を教えてくれます。私にこのような心構えを持つこと、弱者を思うこと、を教えてくれたのはこの学校です。明星学園の多様性の真価、多様性を生きる意味とはここにあると私は思うのです。
私たち人類の文明は未だかつてないほどに進歩を遂げていて、過去のどの時代よりも未来を予測する能力は高まっています。科学は確かに気候変動が起こっていることを示していて、このまま行ったら間違いなく起こるであろう、自然災害や、生まれる悪影響もわかっています。さらに世界中で男女平等が実現するには今から130年近くもかかるということまでも詳細に見えています。でも、こんなに正確に未来を予測する技術をもってしても、あるいは持っているからこそ、というべきなのか、私たちは人類史上一番の暗闇を生きているのではないかと思います。どんな最新のデータを持っている科学者であっても、私たち人類がこれから50年で歩む道はわからないのではないかと感じます。私たちは暗闇を生きています。こんな真っ暗な時を生きる私たちは不安に駆られることもあって当然でしょう。私は人類のこれからが怖いです。
でもそれでも、やっぱりこの世界にまだ希望はあると思いたい。そう思えないと辛いから
ありがちで、くさい比喩を使うとするならば、私たちは流れ星かもしれません。流れ星は私たちなのかもしれません。先行く道が真っ暗で何も見えないのならば、自らが明日を照らす光になればいいのです。
でも想像してください、暗闇を切り開いていく流れ星を。自らを燃やしながら、重力すらも存在しない空間を進む隕石を。孤独に思えませんか。その孤独さゆえに美しいのですが、私には流れ星が孤独に思えてなりません。
でもそれでいいのです。何も問題ありません。なぜなら遠くの地球という星からは、何万人もの人々がこっちを見上げているから。一瞬の輝きすらも見逃すまいと目を見開いてこっちを眺める子どもたちがいるから。
今日ここを去る私たちは孤独です。輝きながらも確かに孤独です。
でもそれでいいのです。なぜなら明星学園という星が遠くにあるから。ここにあるから。
*他の3名の挨拶については、こちらからご覧ください。
*明星会FB(卒業生の活動をご覧いただけます)
 6〜7人のチームになった生徒たちには一人一枚ずつ情報カードが渡されます。そのカードにはゼッケンをつけているランナーの絵が描かれており、『前から◯番目を走っている人のゼッケン番号を当てよ』という指示が出ます。
6〜7人のチームになった生徒たちには一人一枚ずつ情報カードが渡されます。そのカードにはゼッケンをつけているランナーの絵が描かれており、『前から◯番目を走っている人のゼッケン番号を当てよ』という指示が出ます。